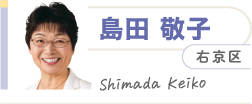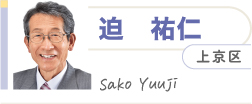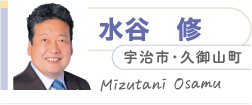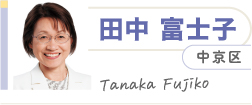2025年2月定例会 議案討論 ばばこうへい議員(京都市伏見区)
日本共産党の馬場こうへいです。議員団を代表し、ただいま議題となっております議案47件中、第1号、第13号、第16号、第28号、第29号、第31号、第33号、第45号、第46号の議案9件に反対し、他の議案に賛成の立場で討論します。なお、第17号議案は保留をいたします。
まず、第1号議案「令和7年度京都府一般会計予算」についてです。
2025年度予算は、来年の知事選挙を前にした、西脇知事の2期目最後となる本格予算です。現在、引き続くコロナ禍の影響に追い打ちをかける異常な物価高と上がらない賃金などにより、格差がさらに広がるなど、目の前の暮らしが壊れ、暮らしも生業も先が見通せないなど、府民生活や地域経済に深刻な影響が広がっています。このため、当初予算に求められているのは、府民に寄り添い支えながら、先行きに明かりを灯すことです。そのためにも、本府には、地方自治体として公の役割を最大限発揮することが求められています。
ところが、予算審議を通じ、国の動きと一体に、府民の願いや実態に寄り添わず、自治体の在り方を根本的に歪める西脇府政の姿が浮き彫りになりました。以下、数点指摘いたします。
第1に、府民生活や、地域経済を支える土台である中小事業者などへの直接支援に背を向け、一部の先端産業・成長産業に偏重した施策で、中小事業者を切り捨てる道を歩もうとしていることです。
これまでも、労働者の暮らしを支えるとともに、中小事業者の人手不足への対策としても急がれる賃上げと、そのための直接支援を求める我が党の質問に、知事は「賃上げは重要」とし、全国で広がる賃上げへの直接支援についても「即効的な効果がある」と認めてきました。しかし、知事は「持続的な賃上げができる環境づくりに取り組む」として、直接支援に背を向け続けてきました。さらに、従業員の賃上げに取り組む事業者を支援するための、金融・経営一体型支援事業の「賃上げ枠」まで、「要件が実態に合わない」「予算枠が少なく広く利用を呼びかけられない」など、制度の改善を求める声に応えず、わずか1年で廃止してしまいました。一方で、産業政策の中心は、「産業創造リーディングゾーン」や「スタートアップエコシステム」など、一部の成長産業やスタートアップを中心にした支援に偏っています。
石破政権は、最低賃金1500円への引き上げを、2020年代に実現すると前倒しを表明しています。そのためには、今後毎年80円~90円の賃上げが必要です。直接支援をしないということは、中小企業が99.8%を占める京都で、国の狙いと同様に、賃上げに耐えられない中小事業者は切り捨てていくということになるではありませんか。
第2に、もはや限界に達している国民健康保険料をはじめとした、医療や介護の緊急の負担軽減に背を向けていることです。
国民健康保険では、府が来年度7.6%もの納付金の引き上げをおこないます。京都市国保で10.35%の引き上げなど、府内の市町村での国保料・税の大幅な引き上げにつながっています。そもそも、府が「国の財政支援とセットで進める」として、国保の都道府県化を先導的に進めてきたにもかかわらず、実際には国からの財政支援は、求めてきた1兆円に対して3400億円にとどまり、市町村が一般財源からの繰り入れなどで何とかこらえてきたものも限界となっています。本来、府としても一般会計からの法定外繰り入れや、「小規模加算」の継続など、値上げを食い止める緊急の手立てを打つべきです。
介護現場でも、国の介護報酬改定の影響で、訪問介護事業所の倒産が相次ぎ、本府でも市町村で1・2カ所しかないところが存在します。人材不足も含め深刻な事態に対し、国に対して緊急に報酬の再改定を求めることや、影響を受ける事業者への直接的かつ具体的な支援が求められていますが、府の対策は国の交付金を使った物価高騰対策などにとどまっています。
今こそ、現場の実情をつぶさにつかみ、解決に役割を果たすことが求められています。
第3に、京都アリーナ(仮称)の建設、大規模開発と一体の先端産業支援や、大阪関西万博のイベントなどにより、財政の硬直化を進め、本来急ぐべきものを後回しにしていることです。
京都アリーナ(仮称)の整備では、今議会に、設計・整備などにかかる288億円の契約案件が追加提案され、先日我が党除く賛成多数で可決されました。また、整備費288億円や付帯設備のリース費60億円の大まかな内容は、予算審議の知事総括質疑で初めて明らかにされました。しかし、住民が再三求めてきた契約前の説明会は開きませんでした。また、北陸新幹線の京都延伸計画は、地下水への影響や残土処理の問題、莫大な事業費と地元負担の問題など、もはや府民的理解を得て進めることが不可能で、知事が「中止」の立場に立つことこそ必要です。さらに、産業政策の中心事業の一つである「産業創造リーディングゾーン」では「拠点整備」として、大山崎町でのアート&テクノロジービレッジ京都の整備に4億円、さらに今後、農林センターの移転に伴うフードテックの拠点整備は数十億円や南部卸売市場の「中食開発拠点」整備など、多額の再開発予算が伴うことが明らかになりました。
大阪関西万博関連事業は、2022年以降、総額22億円を超えています。来年度予算案では、市町村の取り組みへの支援として実施してきた「きょうと地域連携交付金」は、地域づくり事業を大幅に減額する一方で、万博推進事業は倍増するという、市町村の取り組みを万博事業に誘導する予算となっており、他会派の議員からも、「市町村にとっては予算を切られたとの受け止めもある。どう説明するつもりなのか」との質問が出されました。さらに、万博体験のための小中高校生などの入場料支援では、熱中症対策など様々な危惧が指摘されている中で、責任はどうするのかと問われ、理事者は「学校の責任」と答弁するなど、招待は積極的に行う一方で現場の不安には背を向ける態度です。
このように、あらゆる分野に及ぶ大型開発や万博などには巨額の予算をつぎ込む一方で、必要な整備が後回しになっていることも重大です。府立大学の体育館や老朽校舎の建て替え整備は「急ぎたいが現状大きく遅れている」、府立医科大学、府立医科大学付属病院のなどの整備では「設計に何とか入りたいが、いつになるかはわからない」と書面審査で答弁されました。本来急がれるべき施設整備が、現場から計画まで示されているにもかかわらず、今議会でも知事は期限やテンポも示さず「検討していく」と繰り返すのみでした。
第4に、「子育て環境日本一」は、公の役割として急がれる経済的負担の軽減には背を向け、相変わらず風土づくりが中心となるなど、その歪みはさらに深刻になっています。
合計特殊出生率は毎年過去最低を更新し、昨年ついて1.11を記録するに至っています。さらに、京都市内を中心に、子育て世代の人口流出が顕著になるなど、深刻な現状になっています。にもかかわらず、施策の中心は「子育ての楽しさ広げる」として、スポーツ選手と子育て世代の交流や学生と子どもたちの交流など、イベント型の環境整備にとどまっています。さらに、保育現場から批判の声がある「親子誰でも通園制度」の府内全域への拡大や、教育課題では、不登校児童の増加や教職員の長時間労働の問題などから、喫緊の課題となっている少人数学級の実現や全国で広がる学校給食無償化など、府民の願いに背を向けながら、生徒数の減少などを理由に、生徒や保護者、現場の声を無視した府立高校の再編を進めようとしています。
第5に、現場を支える府職員の勤務環境の改善や人材確保に背を向けていることです。
書面審査では、他会派からも「専門職をはじめ、必要な人材確保、育成に一層の努力が必要」と指摘がありましたが、この2年で、技術職員の普通退職が倍増しています。建設交通部、農林水産部、健康福祉部の3部局だけでも、今年度末の退職見込みが90人に達するなど、異常な事態です。府職員労働組合の実態アンケートでは、人手が足りず長時間労働が常態化し、残業代が100%支給されていないとの声が多数寄せられていることや、生活実感として苦しさを感じているとの声が半数に迫るなど、職員全体にわたる労働環境や処遇など、働き続けることに大きな困難があることは明らかです。しかも、メンタルヘルス疾患により7日以上休んでおられる職員が100名を超えています。公の責任を将来にわたって保証するうえで最も重要なのは、職員の計画的な確保と育成です。これまで、正確な勤怠管理や適切な人員体制の確保に正面から向き合ってこなかった本府の責任は重大です。
水道事業に関わる議案について
次に、第13号議案「令和7年度京都府水道事業会計予算」、第16号議案「令和7年度京都府流域下水道事業会計予算」、第33号議案「京都府営水道の供給料金等に関する条例一部改正の件」についてです。次期2025年から2029年については建設負担料金を引き下げる計画となっているものの、施設整備については、府営水道ビジョンでも、広域化・官民連携以外の選択肢を示さず、最も困難な配水管の管理は引き続き市町村に残しながら、利益の得やすい浄水場などを統合するというものになっています。これでは、市町村の自己水を含む清浄で低廉な水を保障するという水道法に定められた公の役割を果たすことはできません。
その他の議案について
第28号議案「京都府勤労者福祉会館条例一部改正の件」
次に、第28号議案「京都府勤労者福祉会館条例一部改正の件」は、城南・中丹・丹後の勤労者福祉会館を「役割を終えた」という理由で廃止しようとするものです。しかし、非正規労働者の拡大、実質賃金の低下など、勤労者の置かれている状況からすれば、必要な職業訓練や相談の充実が求められています。また、公的な施設が少ない地域において、これまで多彩に取り組まれてきた府民の文化・芸術・スポーツ活動、地域の自治活動、避難所などの防災機能など、施設を残し充実することこそ府の責任です。今議会には、存続を求める436件の請願と、1791筆の署名が寄せられました。当事者である利用者や地域の意向も反映されておらず、会館の存続と訓練など会館の機能の継承に、府として責任を果たすべきです。
第29号議案「京都府立高等技術専門校条例一部改正の件」
次に、第29号議案「京都府立高等技術専門校条例一部改正の件」は、府立城陽障害者高等技術専門校を廃止しようとするものです。希望者については他の訓練施設を紹介するとしていますが、同校が担ってきた知的障害者を対象にした全寮制での技能訓練と生活訓練の役割は、他の施設で担えるものではありません。また、条例改正する前に、募集を停止し既成事実を積み上げるやり方も問題です。
第31号議案「京都府立都市公園条例一部改正の件」
次に、第31号議案「京都府立都市公園条例一部改正の件」は、受益者負担の適正化を理由に嵐山公園、宇治公園、山城総合運動公園の各都市公園の使用料を引き上げるもので、昨年12月議会に提案された、手数料や利用料の一斉値上げと同様のものです。施設の維持管理や整備は、本来府が責任をもって計画的に行うべきものです。
第45号議案「指定管理者指定の件(公営住宅吉田近衛団地等)」
次に、第45号議案「指定管理者指定の件(公営住宅吉田近衛団地等)」は、京都市内の府営団地、府営住宅25団地の指定管理を引き続き、株式会社東急コミュニティーに指定するものです。格差と貧困が広がる中で、経済的に最も支援を必要とする方々に、住宅を保障するセーフティーネットとしての府営住宅の役割は、これまで以上に重要であり、京都府が公に住民に寄り添った管理運営をする責任があり、反対です。
第46号議案「関西広域連合規約変更に関する協議の件」
次に、第46号議案「関西広域連合規約変更に関する協議の件」は、関西広域連合の副連合長を1人から3人に変更する議案です。広域連合は、関西財界と車の両輪となって、大阪・関西万博や北陸新幹線などの大規模開発を推進してきました。機能を強化するための規約変更は行うべきではありません。
第17号議案「京都府人権尊重の共生社会づくり条例制定の件」
最後に第17号議案「京都府人権尊重の共生社会づくり条例制定の件」についてです。
人権は日本国憲法で「国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない」「侵すことのできない永久の権利」とされている通り、人が生まれながらに持つ、侵すことのできないものです。しかし、不当な差別や人権侵害、インターネット上での誹謗中傷など新たな問題も起こっており、その防止や被害者の救済をどう図るのかなどが問われています。
条例案には、昨年12月13日から本年1月5日までの短期間のパブリックコメントに97団体255件もの多岐にわたる様々な意見が寄せられました。また、その後も府や議会に対して意見が多数よせられています。このように、人権にかかわる問題は、極めて多岐にわたるため、条例案を作る段階から幅広い府民の声を聞き、丁寧で真摯な議論が必要です。今回の条例案提案にいたる府の取り組みには、その点、不十分であったことは明らかです。さらに、条例を作る以上、具体的に起こっている事象やどのような対策が必要なのかなど、立法事実を踏まえた議論が当然必要であり、その点にも課題があります。
このため、議決を急ぐのではなく、丁寧な府民的な議論を積み重ねることが必要なため、本議案の態度は保留します。
なお、仮に本条例案が可決し、条例を実施するのであれば、懇話会の人選には慎重な検討が必要であること。また、運用に当たっては立法事実に基づいた実効性ある計画の策定を求めておきます。
以上で討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。