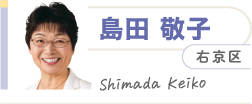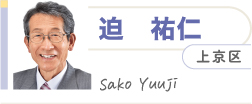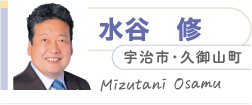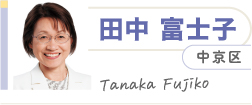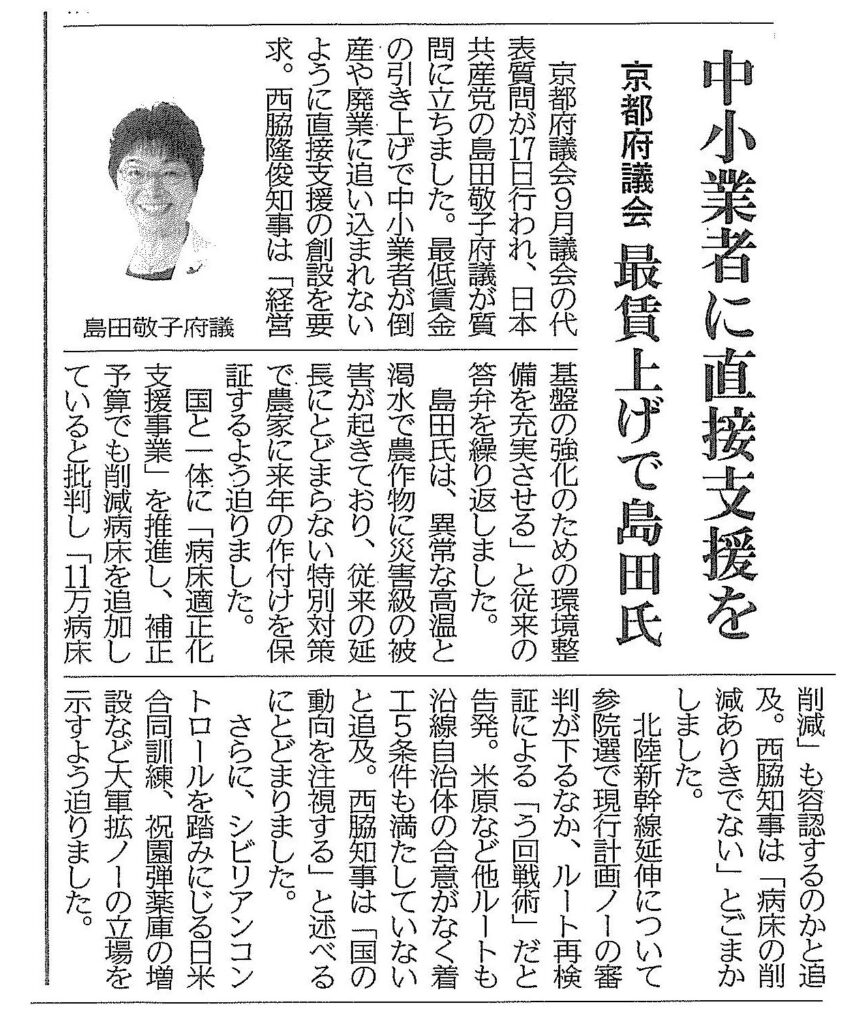9月17日に行われた京都府議会代表質問での、島田けい子議員【京都市右京区】の質疑(大要)をご紹介します。
しんぶん赤旗 2025/09/19
府民の声にこたえて消費税減税、賃上げ支援の実現を
【島田議員】日本共産党の島田敬子です。会派を代表し、先に通告しております数点について、知事に質問いたします。
質問に入ります前に、議長のお許しをいただき、一言申し上げます。先に行われました参議院選挙で、日本共産党は京都選挙区で議席を失うなど議席を後退させる結果となりました。ご支援をいただいた皆さまに感謝申し上げますとともに、広く有権者の皆さんのお声を今後に生かし、捲土重来を期す決意です。何より、皆様にお約束した公約実現に全力を尽くしてまいります。
昨年の衆議院選挙につづき、参議院でも自公政権与党が少数に追い込まれる結果となりました。裏金政治に無反省、物価高騰等に無策の経済対策、アメリカいいなりの大軍拡など、国民の深刻な暮らしに向き合わない政治を変えてほしいという国民の皆さんの厳しい審判の結果です。
一方で、排外主義の危険な逆流が台頭したことにも不安が広がっています。この夏の高校野球では初戦を突破した京都国際高校の生徒たちに対する差別的投稿がSNS上で相次ぐなどの事態が生まれ、本府も削除要請をされました。排外主義を許さず、一人一人の尊厳を守り、人権が尊重される平和な社会にするために、国、自治体、政治家の毅然とした対応が求められております。
新しい政治情勢の下、国の政治のおおもとを、国民本位に切り替えるとともに、地方政治の役割も大きく問われております。知事や府議会も私たち試されています。これらを踏まえ、知事の明解なる答弁を求め、質問に入ります。
今回の選挙は物価高騰から府民の暮らしをどう守るのかが問われました。
第一に、消費税減税と賃上げ支援について伺います。
トランプ関税の影響もあり、今年度の国内総生産実質成長率は低下し、民間企業の経常利益や個人消費が伸び悩み、2024年京都府企業の倒産件数は、建設業で過去10年で最多となるなど、厳しい現状が、帝国データーバンクの調査等で明らかになっています。
今年6月発表の京都商工会議所・経営経済動向調査では、継続する物価上昇に伴う内需の減退、米国の関税政策を巡る不透明感の強まりなど国内経済への影響懸念から景況判断は前回予測を大幅に下回る結果となり、当面の経営上の問題点としては、「原材(燃)料高」が15期連続第1位の50.8%を占めたほか、「求人難」「受注・売上不振」「人件費の増大」を上げておられます。
これら中小企業の置かれた課題を解決し、国民の願いに応えるためには、野党がそろって公約に掲げた消費税減税の実現は喫緊の課題であり、国会での実現のための議論がいそがれます。
まず、消費税減税の緊急減税の問題について伺います。私たち日本共産党は、財源も提案して、消費税の5%緊急減税とインボイスの中止を求め、知事に対して、国へ求めるよう繰り返し要望してまいりました。
世論の多数は消費税減税を求めているのにも関わらず、あくまで「消費税を守り抜く」と減税に反対した自民党や追随した公明党が大敗しました。一方、期限付きや、食料品に限定するなど違いはありますが、すべての野党が消費税減税・廃止を掲げ、これに対して、国民の強い期待が寄せられたことは明らかです。
8月24日共同通信の世論調査では、政府・与党は「消費税の減税を受け入れるべきだ」と答えた人が61,5%にのぼっていました。さらに、候補者アンケートでは、参院選当選者の6割超が減税・廃止を主張していることが判明しています。
そこでまず、伺います。参議院選挙で示されたこれらの民意についてどのような認識をお持ちですか。また、消費税減税の必要性についてはどのように考えておられますか。お答えください。
8月27日の京都地方最低賃金審議会は、現行時間額1,058円を64円引上げ、1,122円にすることが適当であると答申しました。答申には、昨年に引き続き、物価高騰対策の実施や、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境の整備等を求める付帯決議が盛り込まれ、減税や社会保険料の軽減措置など公的負担の軽減など賃上げの原資確保につながる直接的支援を求める内容となっています。
石破自公政権は「5年後までに全国平均1500円」を掲げていますが、今回の引き上げ幅はそのために必要な毎年7.3%の引き上げにも及びません。京都総評の調査結果では若者が、京都で普通に暮らすためには時給1900円が必要との結果が発表されています
他方で、中小企業はどうか、先日、商工会議所の方のお話を聞きましたが、昨年の引き上げでは踏ん張った企業も今回の引き上げでは廃業を考える業者が出てくるとの危機感を示されました。
答申が言うように、最低賃金の引き上げが中小企業・小規模事業者が倒産廃業に追い込まれないよう、中小企業への直接的支援を行う新たな支援制度の創設が必要です。先の通常国会では、わが党が、国の直接支援の検討を要求したのに対し、石破首相も、「それぞれの地域にふさわしい活用を国の財政を用いて支援する」と答弁しました。
そこで伺います。知事は、記者会見で、今回の最低賃金引き上げについて、「引き上げ幅、レベルについて一定妥当だ」と評価し、補正予算案で「経営基盤強化推進事業」として、最低賃金引き上げ額以上の賃上げを要件とした設備投資等への支援として2億8000万円を計上されましたが、これで、厳しい現状におかれる府内中小企業の事業継続が図れるとお考えでしょうか。お答えください。
農家への価格保障・所得補償、高温・渇水被害への災害級特別対策を
【島田議員】次に農業・農村支援について質問します。
異常気象による高温と渇水で北部地域を中心に深刻な被害が広がり、地域存亡の危機に直面しているところも出ています。党府会議員団として、丹後地域、中丹地域の農家の現状を調査し、国への緊急要望も行ってまいりました。わたくしも府下各地の農家を訪問しお話をお聞きしました。大きなひび割れが幾重にも走る乾いた田んぼに穂が出ないまま立ち枯れたものなど惨憺たる現状も見てまいりました。
「雨明けが例年より20日も早く、心配していたが、穂が出る1番大事な時期に水がなく、ため池頼みの田んぼは全滅です」大規模に圃場整備した田んぼでは高低差もあり、隅々に水が行き渡らず、コメの品質が落ち、収穫量は大幅に減少する見込みと肩を落とされていました。昨年はカメムシにやられたり、シカや猪に荒らされ全滅し、今年は渇水で全滅という農家もありました。
地域の21ヘクタールを請け負うある営農法人では、担い手農家は僅かに2軒になり、理事は全員70歳以上で、その他の兼業農家も3分の1が75歳以上で、「都会に出て行った子どもが帰ってくる見通しもなく、米を作り続けられない。あと数年しか持たない。中山間地のコメづくりから撤退することも考えている」と話されました。
地域のコメ作りを一手に引き受けている30代の子育て真っ最中の若手農業者は、このようなことが毎年繰り返されれば、コメ作りを続けられないと先行きの不安を訴えておられました。
本府では、8月1日、6月補正予算により実施している「農業経営基盤強化(高温対策等)事業」に新たなメニューとして「水稲渇水対策等支援事業」を追加し、募集をしましたが、「ポンプやホースを買いに行ったが売切れで品物がなかった」「ポンプの燃料代、散水車の料金の負担が大きい」「募集期間が短い」「対象期間内に機材の購入ができない」など、拡充を求める声も寄せられておられました。
本府は、8月4日になってやっと、渇水緊急対策会議を開催し、宮津湾浄化センターの放流水や福知山工業団地の工業用水を活用した配給水支援を行い、効果が出ているところもありますが、間に合ってない地域も多数残されております。
コメに加え、トマトや万願寺、スイカ、小豆、果樹等にも高温・渇水の影響がひろがっており、水稲や園芸作物に対する高温や渇水対策支援事業等の通年実施、支援規模の拡充を求める声も上がっております。
そこで伺います。知事は、8月22日の記者会見で、「収穫量や品質への影響について実態把握に努め、被害が出るようであれば農業保険の適用について案内し、伴奏支援していく」と述べておられますが、今夏の異常な高温と渇水被害の現状はまさに災害級であり、現在の農業共済や収入保険では救えないのが実態です。制度の改善はもちろん、従来施策の延長にとどまらない特別の対策を緊急に行い、来年の作付けを農家に保証する事が必要と考えますが、いかがですか。
また、今後も予想される渇水問題では、ため池や井戸等、農業用水のための農業水利施設の老朽化対策や計画的な設置、用水路の整備など地域基盤の改良が急がれますが、いかがでしょうか。
今年も新米の価格が高騰しています。農薬や燃料、資材、農機具などの生産費が高騰していることや、異常高温、渇水で作柄の悪化が予想される中で、集荷競争が激化しています。何より、需要に対する生産量不足が根本的原因です。昨年夏、わが党が本府に申し入れをした際には国も、本府も生産量の不足は否定し、「新米が出てくれば落ち着く」などとして備蓄米の放出も行いませんでした。
歴史的な米価高騰が家計を直撃し、批判が高まる中で、政府は今年になって備蓄米の放出を始めました。8月5日の閣僚会議でやっと、生産量不足が価格高騰の原因と認め、増産に方針転換するというものの、具体策は、従来の経営の大規模化等、自民党農政そのままです。
加えて トランプ関税による農業破壊への懸念が広がっています。農業・食料分野では、日本が米国産米の輸入を直ちに75%増やすとともに、トウモロコシや大豆、肥料、バイオエタノール、持続可能な航空燃料など80億ドル(約1兆2000億円)の米国製品購入を合意したとされています。2026年度予算要求では「コメ増産」を明記しましたが、一方でコメ輸入拡大を安易に続ければ、日本農業は衰退することになります。打撃を受けた農林水産業支援の緊急対策とともに、国産米の需給と価格安定に責任を持つ政策への転換が必要だと考えます。
そこで伺います。6月議会では、知事は「米の需給と価格の安定化に向けて必要な需給量の見通しを示した上で米政策を企画・立案と生産性向上、付加価値向上などの独自事業により、農業者の所得向上を図ると」と、価格保障や所得補償を拒み続けておられますが、それでは地域の農業が存続できないことは明らかではないでしょうか。今必要なことは輸入自由化路線をやめ、価格保障と農家への所得補償を行い、農家が安心して増産できるよう、生産体制を強化することです。いかがでしょうか。
また、「トランプ関税」は日本の食の安全を脅かし、農業を破壊するものだと考えますが、知事の認識はいかがでしょうか。
【西脇知事:答弁】島田議員のご質問にお答えいたします。 消費税についてでございます。物価高騰が家計や企業経営に影響を与えており、こうした負担軽減のための対策の一環として、消費税減税や廃止が参議院選挙の争点の1つになったものと承知しております。消費税につきましては、全世代型社会保障に必要なものとして法律で税率の引き上げが行われたものであり、そのあり方につきましては、少子高齢化社会における我が国全体の社会保障財源の問題として、国において検討されるべきものと考えております。また消費税収の約4割は地方税財源であり、社会保障関係経費の増加や物価高騰などによって地方財政が厳しい状況にある中で、地方が安定的に行政サービスを提供していくためにも、地方への影響を十分考慮いただくよう本年6月に全国知事会からも国に緊急提言を行っております。消費税減税の是非につきましては、こうした社会保障財源や地方財源の確保の観点から、国におきまして将来世代の負担に十分配慮した丁寧な議論をしていただきたいと考えております。なお京都府といたしましては、 府民生活と地域経済を守るため、物価高騰対策といたしまして今定例会で提案している補正予算案を含め 、令和7年度予算に必要な事業を盛り込んでおり、これらによる支援に着実に取り組んでまいりたいと考えております。
次に賃上げ支援についてでございます。賃金の引き上げが持続的に行われるためには、中小企業が原資となる収益を確保できるよう、経営基盤の強化を図るための支援を重点的に行うことが重要だと考えております。このため京都府におきましては、累次にわたり賃上げができる環境整備のための支援を行ってきたところでございます。また国におきましても賃上げこそが成長戦略の要との考えのもと、最低賃金を2020年代に全国平均1500円とする目標を、いわゆる骨太方針2025に示され、先月27日には京都地方最低賃金審議会が京都労働局長に対しまして、府内の最低賃金の64円引き上げを答申したところでございます。これらの状況を踏まえ、この定例会におきまして中小企業の賃上げが可能となるような経営基盤の強化を支援するための予算案を提案しているところでございます。京都府におきましては、生産性向上への支援や人手不足対策、金融支援と金融支援が一体となった伴走支援など、様々な観点での施策を行っているところであり、 今回の予算案でさらに施策の幅を広げ、経営基盤の強化に向けた支援を充実させることで、府内中小企業の事業継続を図ってまいりたいと考えております。今後とも中小企業の経営を守るため、あらゆる施策を総動員して全力で取り組んでまいりたいと考えております。
次に京都府の農業、農村支援についてでございます。本年の記録的な高温渇水による農作物被害への対策につきましては、被害を受けた農業者への緊急的な支援とともに、常態化する高温渇水に備えた生産基盤の強化が急務だと考えております。緊急的な支援につきましては、8月4日に開催いたしました 京都府農業渇水緊急対策会議での決定に基づき、現場要望を踏まえた用水ポンプの購入と浄化センターの放流水や工業用水の活用に必要な給水活動を支援してきたところでございます。生産基盤の強化につきましては、次期昨に向け安定した収量と品質が確保されるよう、渇水被害を受けた水田への土壌改良資材の支援による土づくりや高温対策として効果のある機器資材の導入、高温耐性品種の普及拡大に必要な予算案をこの定例会に提案しているところでございます。地域の農業基盤の改良につきましては、 安定的な農業用水の確保に向け、ため池や用水路等の機能を維持向上することが重要なことから、老朽化や機能性の診断を行い、今後の劣化予測や対策方法を取りまとめた機能保全計画に基づき、順次整備を進めているところでございます。引き続き機を逸することなく必要な対策を講じることにより、持続的な農業の実現に取り組んでまいりたいと考えております。
次に農業者への所得支援についてでございます。近年の資材高騰や気候変動など農業経営の厳しさが増す中、京都府では農業者が安定的に所得を確保できるよう、収入保険など国のセーフティネットへの加入を促進しつつ、府独自に省エネ、高温対策機器の導入や販路拡大など、生産、販売両面から経営力を強化し、長期的に効果が期待できる支援を実施してきたところでございます。国におきましては、農産物の適正な価格形成に向け、生産コストを考慮した取引を義務付ける法律を制定し、来年4月以降に施行することとしており、京都府といたしましては国に対しまして、条件不利な中山間地域におきましても経営が成り立つよう産地条件を考慮したコスト仕様の策定など、実効性のある仕組みの構築を要望しているところでございます。
米国の関税措置につきましては、コメをはじめとする農産物は食料安全保障上重要な役割を担っていることから、影響を最小限に努めるよう国におきまして関税交渉が行われ、コメについてはミニマムアクセス米の枠内で米国からの輸入量を増やすことが合意され、現在詳細な確認を行われているものと認識しております。引き続き府内企業、府内事業者への影響について丁寧な情報収集に努めますとともに、対策が必要と認められる場合には迅速に対応してまいりたいと考えております。
【島田議員:指摘要望・再質問】消費税減税の問題も賃上げ問題もこれまでの答弁を繰り返されて、想定通りの答弁になったわけですけど、消費税の減税の必要性については明確な答弁がありませんでした。物価高騰に苦しむ府民の声に答えることもなく、選挙で示された消費税減税を求める民意に背を向ける自民党政治の延命に手を貸すことは許されません。指摘をしておきます。
1点質問します。賃上げについてでございます。今回の大幅な賃上げは後押しをしなければならないというお立場だと思うんです。記者会見で全国制度としてやった方が効果的だと。中小零細業者の大きな負担である社会保険料の免除軽減等についても実施すべきでありますし、これらについてですね 答申にも繰り返されておりますが、国の動向は今どのようになっておりますかとお聞きしたい。また補助金を直接的支援するのは財政的に困難と、財政の使い道として体力をつけていただくのが効果的だとも述べてこられました。中小企業が倒産廃業に追い込まれても構わないというお考えなのかどうかお聞かせください。
農業農村支援についてでございます。補正予算について一定評価 いたしますが、現場の実態を踏まえて必要な増額なり、きめ細かい運用をお願いしておきますが、今回の被害を災害級と認識し、それにふさわしい緊急対策と制度の改善を重ねて要望いたします。
農家の皆さんが安心して農業を続けられるには最大の問題は所得補償、価格保障です。このことについてはやっぱり今回も明確な答弁がありません。農業センサスによりますと10年間に基幹的農業従事者は3分の1以上減少し続け、農地の維持が困難な深刻な状況です。これまでの対策では限界だと考えられませんか、お答えください。
【知事:再答弁】1点目、必ずしも質問の趣旨を的確に取られているのか分かりませんけれども、国の動向ということであればですね、税につきましては当然ながら新しい政権が誕生した後、税については一般的な議論が与野党間で行われると思っておりますけれども、そうした中で税というのは一部の税 だけについて議論するのではなくて、当然国民負担またそれによって充てられます行政サービスとの兼ね合いの中で総合的に議論していただきたいんですが、我々地方自治体の立場としては、何においても 我々が行います行政サービスのための地方税財源につきましては、必ずきちっとそれを考慮した上での丁寧な議論をお願いしてまいりたいと思っております。
中小企業につきましては、当然物価上昇を上回る賃金の引き上げが経済の好循環をもたらすと思っておりますけれども、中小企業がその賃上げに必要な収益を確保できないと、結局は中小企業が倒産することによって雇用も失われるということから、このバランスの中で必要な施策を講じるべきだと思っておりまして、我々としては財政の効率性から考えて、中小企業が賃上げに必要な体力に必要な経営基盤を強化するために支援をしてまいるのが正しい道だと思っております。
農業につきましては、今般の高温渇水については災害級というご発言ありましたけれども、極めて異常な気象によるものと思っておりまして、そのために緊急渇水対策会議も開かせていただき、浄化センターの水とか工業用水の活用もさせていただいたところでございます。その認識については変わりはございません。けれどもいずれにしても、これからもこの高温渇水が続くとすれば、そういう中でもその耐性に優れた品種ですとか水の用意とか、そういう次期作に向けての対策も含めて予算を提案させているつもりでございまして、ご指摘のありました農業人材の確保も含めてこれからも農業が持続可能な作業して続くように全力で支援して参りたいと考えております。
【島田議員:指摘要望】2月議会では光永議員の質問に対して、知事は京都で地域経済に責任を持つ、府として責任を負うのはその通りと答弁されました。京都の経済、雇用に責任を持つ知事として、国がやらないのなら自ら率先して中小企業支援をする。答申に盛り込まれているように、色々な要件をつけるのではなく、直接的な支援が求められると答申されておりますので、是非中小企業の営業が存続できるよう、1社たりとも潰さないよう検討いただきたいと要望をいたします。
農業農村支援についてもですね、先ほど申しました通りであります。このままでは時給10円という現状、小規模農家も大規模農家もみんな農業存続を頑張れるかどうかの緊急事態です。なのでやはりヨーロッパでも実施されている所得補償、価格保証これまでの議会でも要望しましたけれども、踏み出すべきですし国に対しても要望し、また京都では昔「西の農林省」と言われた時代がありました。京都食管という制度がありました。この先達の取り組みを検証し、ぜひ学んでいただきたいと要望をしておきます。
医療と介護の危機打開について
【島田議員】次に、医療と介護の危機打開について質問いたします。医療機関は過去最大規模で倒産・廃業がすすみ、深刻な経営危機に陥り、地域の医療提供体制が壊れかねない危機的状況です。
6月定例会で浜田議員の質問で、緊急措置を行なうことを求めたことに対し、知事は、「医療機関や介護事業所に対する財政支援などについて要望する」との答弁にとどまる一方、国言いなりに「病床適正化支援事業」を推進しています。この事業には全国で5万4000床もの活用申請があり、そのうち京都府は2047床となっています。6月補正で第一次内示分139床、第二次内示分152床が追加の見込みであり、各圏域での地域医療構想調整会議の場での議論が行われています。さらに、日本維新の会や国民民主党が、自民・公明の与党と「医療費年4兆円削減」で合意し、「病床11万床削減」を進めようとしています。
物価高騰・資材高騰による病院経営の悪化、看護師不足などによりやむなく病床閉鎖を強いられている医療機関の診療報酬の緊急改定を求める声に応えず、医療社会保障の予算を削るために、病床削減を進めることは許されません。
そこで伺います。6月定例会では、知事は、すでに「休床中、もしくは、休床予定のベッドであり、医療に支障はない」と答弁されましたが、自治体病院を含む更なる病床削減を推し進めるのですか。また、全国の病床数の1割にのぼる11万床ものベッド削減を容認するのでしょうか。
また、さらに「地域包括ケア構想」について、知事は、「地域の医療ニーズを踏まえて、丁寧な議論を圏域ごとに行い、将来にわたって府民が安心して医療を受けられる体制を検討して整備に取り組む」と答弁されましたが、現実には、地域での必要な医療からの議論ではなく、まさに医療費抑制先にありきの議論が進められており、これでは患者の命も地域医療も守ることはできないと考えます。いかがですか。
医療提供体制の削減とともに自公政権が進めているのが患者の負担増です。
国民の反発で凍結されている高額療養費制度の上限額の引き上げに加え、OTC類似薬類似薬の保険外しが狙われています。「骨太の方針2025」において2025年末までに予算編成過程で十分な検討を行って、早期に実現可能なものについては26年度から実現するとしています。
OTC類似薬が保険外しされれば、患者負担は数倍から数十倍もの負担増になります。保険外しは、指定難病制度や子育て支援医療など福祉医療で負担が軽減されている人にも過大な自己負担となります。「骨太」では「現役世代の保険料負担軽減」がうたわれていますが、保険料が若干安くなったとしても、保険から外された薬の購入費用で家計負担は今よりも重くなりかねません。
京都府保険医協会のアンケートでは、OTC類似薬を保険外しに反対が約7割に上り、実際にOTC薬の服用で重症化して来院した患者があるが4割に上っており、「誤った自己判断での服薬で病状が悪化する懸念を述べておられます。
そこで伺います。全ての世代で患者の負担増と健康悪化を招きかねない高額療養費制度の上限引き上げやOTC類似薬の保険外しについて、反対すべきと考えますがいかがでしょうか。
また、介護報酬に引き下げで、在宅介護の要の訪問介護事業所が一つもない自治体が全国で広がり、府内では笠置町でゼロ、伊根町、大山崎町、井手町、南山城村、和束町では一か所しかありません。
先日、和束町の社会福祉協議会でお話を伺いました。国の訪問介護報酬の引き下げや人材確保の困難に加え、移動時間やコストが報酬に反映されず、事業所は赤字経営を余儀なくされています。訪問介護事業の主な担い手になっている社協の事業を存続させることは高齢者の生活を支える重要な基盤であることから、町が赤字分を補填し経営を支えていました。人材確保のためのさらなる支援も求めておられます。
そこで伺いますが、6月定例会で、知事は、「人材不足が顕著であり、収入が減少しているなど、特に支援が必要と考えられるところは必要な介護サービスの提供が継続できるよう、介護事業者への支援に取り組む」と答弁されました。本府として、介護報酬の緊急改善を国に求めるとともに、訪問介護事業継続のための独自の支援を行い、市町村を支援すべきですがいかがでしょうか
エネルギー政策と原発新増設、乾式貯蔵施設建設計画について
【島田議員】次に、エネルギー政策と原発新増設、乾式貯蔵施設建設計画について伺います。
2011年東日本大震災、福島原発事故から14年になります。広範な放射能汚染によって、多くの方が故郷を追われ、いまだに約4万5千人が地域に戻れずにいます。放射性物質を含んだ汚染水は1日80トンのペースで増え続け、溶け落ちた核燃料は取り出しの見通しさえ立ちません。
福島原発事故は全く終わっていないにもかかわらず、国は今年2月に第7次エネルギー基本計画を閣議決定し、これまでの再生可能エネルギー「最優先の原則」や「原発依存度を低減させる」記述を削除し、原発の「最大限活用」を明記いたしました。
近年、国は高コスト化する原発の新設を後押しするため、建設費や人件費などの固定費を原則20年間得られる「長期脱炭素電源オークション」制度を創設し、原発建設費の上振れ分を電気料金に上乗せして回収する支援策までつくろうとしています。
また、経産省は「優先給電ルール」によって、原発を最優先にしているため、再生可能エネルギーで発電された電力の出力が抑制され、大量に捨てられております。これにより、再エネ事業者は売電収入が押し下げられ、再エネ拡大の障害にもなっています。
このように原子力発電は、事故が起これば取り返しのつかない被害が発生するばかりか、もはや経済合理性も無く、再エネ導入の障害にもなっています。自民党は原子力産業協会会員企業から70億円以上の企業献金を受け取っていますが、これらに応えて新たな原発安全神話の上に原発新増設を進めているのです。とんでもありません。
そこでお伺いします。本府はこれまで「徹底した省エネ化と再エネの最大限の導入により、原子力発電に依存しない社会」を目指す立場を示してこられました。その立場に立つなら、原発を最大限活用する第7次エネルギー基本計画にはきっぱり反対すべきではありませんか。
関西電力は、使用済み核燃料を輸送兼用の専用キャスクに密封し、鉄筋コンクリート製の格納設備で覆うという「乾式貯蔵施設」の設置を、高浜、美浜、大飯の原発敷地内で計画しています。関電の使用済み核燃料プールは、今年2月現在で約87%が埋まっており、あと数年で満杯になり、原発の運転ができなくなります。これを避けるために、使用済み核燃料を乾式貯蔵施設に移して、40年越え50年越えの老朽原発を続けようとしています。乾式貯蔵施設は、中間貯蔵施設への運搬までの一時的な保管と言いますけれども、その具体的な計画は示されず、青森県六ケ所村の再処理施設の稼働は27回も延期されています。乾式貯蔵施設が出来てしまえば原発敷地内で半永久的に貯蔵される事にもなります。
市民運動の皆さんが昨年の6月~11月に、高浜原発のPAZ、UPZ圏内の住民である府北部の7市町に住む皆さんを1軒1軒訪問されまして、857人のアンケートを集められましたが、「乾式貯蔵の計画を知っているか」の問いに約8割が「知らない」と回答し、また乾式貯蔵について「電力会社や自治体は住民に説明する必要があると思うか」の問いには82%が「説明するべき」と回答しています。
原発から5キロ圏内のPAZ区域、30キロ圏内のUPZ圏内で暮らす府民にさえ直接知らされることなく、危険な老朽原発の運転継続を認めることにもなる関西電力の乾式貯蔵施設の建設に、反対すべきと考えますが、いかがでしょうか。
昨年の能登半島地震では、志賀原発から30キロ圏内の通行止めは32か所、う回路もない場所が8か所、道路寸断により孤立した集落は14地区に及びました。116か所のうち18か所のモニタリングポストで線量のデーター通信ができなくなり、屋内退避施設は14施設が損傷、6施設が放射線防護機能を失いました。地震と原発事故が同時に起これば、避難もできず、屋内退避もむつかしいことが証明されています。
ところが、原子力規制員会が6月に発表した原子力災害対策指針の改定案では、能登半島地震の教訓を省みることなく、自然災害と原発事故という複合災害についての言及がありません。UPZ30キロ圏内の住民は避難でなく、「屋内退避を実施することが主要な防護措置である」と記していています。UPZ圏内では、屋内退避から避難に切り変わる場合も安定ヨウ素剤の服用も必要ないとされるなど、重大な問題があります。
そこでお伺いします。複合災害を想定せず、現行指針からも大きく後退する原子力災害対策指針の改定について、どのようにお考えですか。少なくとも、現行からも後退する改定案は撤回し、再検討するよう、国に求めるべきです。いかがでしょうか
【知事:答弁】地域の医療提供体制についてでございます。今後の急速な高齢化と人口減少が見込まれる中、地域の皆様が安心して医療を受けられる体制を構築するためには、将来を見据えて、効率的で質の高い医療を持続的に提供する体制の構築が必要であると考えております。そのため、京都府では、地域医療構想調整会議におきまして、各地域の事情を踏まえ、医療機関の連携や役割分担の見直しなどの検討を進めており、病床の削減ありきではなく、将来必要な医療体制を整備する観点で取り組みを進めているところでございます。
また、病床数適正化支援事業につきましては、経営状況が厳しい医療機関の入院医療の継続を目的に実施しており、事業の実施にあたっては、京都府として、対象となる医療機関に対し、病床の削減が地域医療や新興感染症への対応に影響を及ぼさないことを確認しているところでございます。また、地域医療構想調整会議におきましても、対象医療機関及び削減病床数を報告し、地域の医療関係者などから御意見を伺うなど、必要な地域医療体制を確保する観点で議論を行っているところでございます。引き続き、府民の皆様が将来にわたって安心して医療を受けることができるよう、地域の医療関係者などのご意見を伺いながら、必要な体制の確保に努めてまいりたいと考えております。
次に、OTC類似薬の医療保険における給付のあり方等についてでございます。国は、現役世代の負担軽減策として、OTC類似薬の保険給付の見直しの検討を進めることを今年のいわゆる「骨太の方針」に盛り込んでいることは承知をしております。この秋からは、社会保障審議会などで、保険適用を見直す薬の種類や対象の病気について具体的な議論を行う方向とされており、OTC類似薬の具体的な定義や見直しの方向性につきましては、今後明らかになっていくものと考えております。また、高額療養費制度につきましては、国は、患者団体などの意見を踏まえ、ことし8月に予定していた負担上限額の引き上げを見送り、改めて制度の在り方が検討されているところでございます。これらの見直しによる影響は現時点では明らかではありませんが、患者負担が急激に増えることがないよう、また重症者や長期治療が必要な方へ配慮がなされるよう、全国知事会を通じて国へ求めているところでございます。
京都府といたしましては、医療保険制度の見直しは、患者負担への十分な配慮のほか、医師や薬剤師の適切な関与、国民皆保険制度の堅持などを総合的に踏まえる必要があると考えており、丁寧な議論がなされるよう今後とも国に求めてまいりたいと考えております。
次に、訪問介護事業所への支援についてでございます。介護事業所は、国が定める公定価格により経営を行っていることから、国の責任において介護報酬の改定や補助制度の創設などの対策が行われるべきと考えております。引き続き、介護事業所に対する財政支援などを強く要望してまいりたいと考えております。また、介護報酬改定までの間の臨時的な事業として、本年6月定例会において御議決いただきました訪問介護等サービス提供体制確保支援事業におきまして、人材確保や経営の安定化を推進することとしており、現在、交付決定に向けた審査を行っているところでございます。なお、介護事業所における働きやすい職場づくりを進める京都福祉人材育成認証制度の推進のほか、昨年度からは生産性向上人手不足対策事業を実施するとともに、去る5月30日には京都府介護福祉職場業務改善支援センターを開設し、事業所の状況や課題に応じたきめ細かな相談支援を行っているところでございます。今後とも、府民の皆様に必要な介護サービスの提供が継続できるよう、介護事業所への支援に取り組んでまいりたいと考えております。
次に、エネルギー政策についてでございます。京都府におきましては、「総合計画」におきまして、徹底した省エネルギー化と再生可能エネルギーの最大限の導入、エネルギーの地産地消の推進により、原子力発電に依存しない自立分散型のスマートな社会の実現を目指すこととしております。
国の第7次エネルギー基本計画におきましては、エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入することを基本に、再生可能エネルギーか原子力化といった2項対立的な議論ではなく、脱炭素効果の高い電源を最大限活用することが必要不可欠であるとされており、従来の恐怖との立場と同じ方向を目指しているものと考えております。引き続き、徹底した省エネルギー化と再生可能エネルギーの最大限の導入に取り組んでまいりたいと考えております。
次に、乾式貯蔵施設についてでございます。脱炭素効果の高い電源の一つとして原子力を活用するに当たりましては、国が責任を持って乾式貯蔵施設を含む使用済み燃料対策に対応すべきものと考えております。乾式貯蔵施設につきましては、UPZ圏内の7市町と京都府で構成する高浜発電所に係る地域協議会幹事会におきまして、昨年8月に関西電力から設置計画の説明を受け、本年7月には原子力規制庁から計画の審査内容の説明を受けたところでございます。その際、国に対しましては、引き続き厳格な審査に基づく検査・指導の徹底を求めるとともに、関西電力に対しましては、府民の不安を払拭するための分かりやすい情報発信を強く求めたところであり、関西電力では、今月15日からUPZ圏内の世帯を対象に、新聞折り込みにより乾式貯蔵施設に関する情報発信をすでに開始されているところでございます。
次に、自然災害と原子力事故の複合災害についてでございます。国の「原子力災害対策指針」におきましては、複合災害にも対応できる基本的な考え方として、平成24年の制定当初から、被曝を直接の要因としない、健康等への影響も抑えることが必要と定められており、この定めは、9月10日に原子力規制委員会で決定された指針の改正でも変更がないところでございます。これは、国の防災基本計画におきまして、複合災害が発生した場合においても、人命の安全を第一とし、自然災害による人命への直接的なリスクが極めて高い場合等には、自災害に対する避難行動を取り、自然災害に対する安全が確保された後に、原子力災害に対する避難行動をとることを基本とするとされていることとも整合しております。これらを踏まえ、国の原子力規制委員会におきましては、本年3月、原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム会合報告書におきまして、複合災害時には自然災害への対応を優先することを基本とし、屋内退避が難しい場合にはUPZ外へ避難することとされており、今後、屋内退避の具体的な運用の考え方を示すとされております。京都府におきましては、「京都府地域防災計画」におきまして複合災害を想定した取り組みを定めているところであり、備えに万全を期すため、陸路、海路、空路の複数の避難経路による避難体制の強化を進めているところでございます。
具体的には、UPZ圏内におきまして避難経路の改善を進めますとともに、自衛隊、海上保安庁と連携した船舶による避難訓練を実施し、孤立可能性のある地域を有する舞鶴市、綾部市が進めるヘリポートの整備を支援しているところでございます。また、これらの避難の実効性の向上を図るため、京都府原子力総合防災訓練におきまして、住民の皆様にも参加いただきながら、陸路、海路、空路による避難訓練を実施しているところでございます。加えまして、市町と連携し、UPZ圏内の社会福祉施設や公民館などを放射線防護機能を有する屋内体施設として整備しているところでございます。京都府といたしましては、引き続き、国に対しまして安全確保対策について責任を持って対応するよう求めますとともに、複合災害を想定し、避難関連施設の整備や実動訓練による避難の実効性の向上など、ハード、ソフト一体で取り組んでまいりたいと考えております。
高齢者狙い撃ちの負担増と給付減には反対を
【島田議員:再質問】答弁ありがとうございます。医療、介護の危機打開でございます。いろいろとやっていると述べられましたけれども、関係医療団体も、そして全国知事会からも緊急要望が何度も出されているぐらい、今はかつてない危機、これが解決のめどが立っておりません。
本府も急性期を中心に病床削減を行ってまいりましたけれども、結果、コロナパンデミックで必要な医療を受けられず亡くなられた多数の命があったことをお忘れでしょうか。新たな地域医療構想を目指し、医療、社会保障の削減、とりわけ世代間分断をあおり、高齢者を狙い打ちにした負担増と給付削減、そのための病床削減や患者負担増が狙いであると私は思っていますが、これに対して断固反対すべきだとお尋ねをしているんです。再度お答えください。
原発問題、先日、舞鶴大浦半島に行ってまいりました。京都府の事業も着々と進んでおりましたけれども、田井の防災センターは80人しか入れないし、成生、そして水之浦漁港、綾部奥環林地区、訪問し、話を聞きましたけれども、能登半島地震後、さらに住民の不安が高まっておりました。「原発が爆発したらもう終わりだ」、「避難しようにも道路が寸断されて逃げられない」、「漁業も農業も、住み続けることさえできない」という声でありました。避難訓練は何回かありましたけれども、そうした訓練も現在していないし、「原発事故は誰がどのように誘導して避難をするのか全く分からない」というのが現場の住民の現状であります。この住民の声をどのように受け止めておられるのか、この際、知事に伺いたいと思います。ご答弁お願いします。
【知事:再答弁】島田議員の再質問にお答えいたします。1点目。御指摘のように、今、地域医療をめぐる状況は、人口減少、少子高齢化だけじゃなくて、疾病構造の変化等も含めて極めて大きく変化しております。そうした中で、いかに公的病院を含めて医療提供体制を構築していくのかということが重要でありまして、地域医療構想調整会議におきまして、医療機関の分担また連携のあり方について見直しの取り組みを進めているところでございます。いずれにしても、病床の削減ありきではなく、将来にわたって地域で必要な医療提供体制をどう確保するかという観点から議論をしておりまして、引き続き、府民の皆様に的確に高度な医療が提供できる体制の構築に取り組んでまいりたいと思っております。
原発の避難についてでございますけれども、私も、復興庁によりまして、福島第一原発の事故によります状況につきましては十分把握しているものでございまして、一旦事故が起こりますと非常に大きな影響があるということから、常に事故も想定しながら準備を進めていくことが重要だと思っております。
そのためには、的確な訓練と避難路等、屋内退避施設も含めたハードの整備、あわせまして進めていくことが重要だと考えておりまして、そのためには、府民の皆様に原発の避難、避難計画、避難訓練について十分認知していただく必要があるということで、そうした広報も含めて取り組んでまいりたいと思っております。
【島田議員:指摘要望】ご答弁ありがとうございます。医療費削減ありきではなく、きちっと地域での声を聞くと、現場の声を聞くとおっしゃいましたので、御努力をいただきたいと思います。全ての府民の皆様、国民に必要な医療を提供することはまさに人権保障の問題だと考えております。ならば、先ほども申し上げましたような国の政策には、やはり住民の暮らしと命を守るために自治体の長としてきっぱり病床削減中止を求めていただくことが必要だと私は考えますので、要望をしておきます。
先日、京都府の総合防災訓練では原発事故による複合災害が想定されておりませんでしたが、別立てで訓練をされるのですかね。国も京都府も福島や能登の事故を忘れたかのようだなと思ったんですけれども、新しい安全神話にとらわれて、住民の頭ごなしの原発新増設、それにつながる乾式貯蔵施設計画については反対すべきであると私たちは考えますし、避難計画についても、後退した指針によらず、より実効性のある計画策定とそして整備を行っていただきたい、要望をしておきます。
府民の合意が得られない北陸新幹線延伸計画よりも在来線の拡充を
【島田議員】続きまして、北陸新幹線延伸計画についてです。7月16日に京都新聞が1面トップで「新幹線ルートを巡り攻防一大焦点に」と報じるなど、この問題は参議院選挙の大争点、京都の争点になりました。
京都選挙区の候補者の選挙結果では、「慎重派・他のルート」や「延伸計画中止」を掲げた候補者に投票したのが98万4000票。「現行推進・計画推進」は20万票と、圧倒的に「現行ルート中止・見直し」を求める審判となりました。
自民党西田候補は、最終版京都新聞の広告で「北陸新幹線は京都府民の合意なしには進められることは絶対にありません」と言わなければならないところまで追い詰められたのです。選挙戦の結果からも民意は明らかに、現行計画はNO!だという府民の審判が下されたのではないでしょうか。
京都市議会6月定例会では、京都市内大深度地下トンネル計画に反対の決議が可決。皆さんの粘り強い運動の結果、どの世論調査でも延伸反対は多数となっております。京都新聞が社説で見直しを論じ、京都仏教会も「千年の愚行」と厳しく批判して50万署名を開始されました。
ところが選挙後、7月21日西田参議院議員は「8年前に決まったこと」と言い、8月1日の読売新聞インタビューでは「正しい情報が伝わっていない。なぜ小浜に決まったのか再検証で分かる」と述べたと報じられております。「再検証を持ち出して迂回戦術で突破を図ろう」という魂胆が透けて見えます。西脇知事は「どういう形で再検証をするのか、しないのかを含めて見守ります」「今までどのルートがふさわしいか発言したことはない。今の段階でも言うつもりはない」「国鉄道運輸機構の動向を注視していく」とのことです。
そこで伺います。現行計画はNO!という民意と共に、舞鶴ルートも沿線自治体の合意が得られず、着工5条件も満たすことはできない現状であると考えますが、いかがですか。そういう認識をお持ちになりませんか。
私共は延伸計画はきっぱり中止し、府議会でも議決したサンダーバードの拡充、在来線の整備拡充や生活公共交通バスの拡充、住民の暮らしのインフラ整備、防災対策こそ優先すべきと考えます。いかがでしょうか。
府民の安全を脅かす弾薬庫整備や基地強化には国に対してNO!を
次に舞鶴海上自衛隊基地及び精華町祝園分屯地における弾薬庫整備など基地強化拡充についてです。今年は戦後80年の年です。府内各地で「二度と戦争はさせない」と平和のための戦争展や原爆資料展などが開催され、多くの人々が平和な世界を願いました。ところが自公政権は戦争への道を足し切るどころか、憲法を踏みにじり大軍拡への道を突き進もうとしています。
防衛省は、「安保3文書」に基づき、他国領土を直接たたく敵基地攻撃能力の保有に向け、国産長射程ミサイルの全国配備計画を公表するとともに、過去最大の8兆8454億円に及ぶ概算要求を発表し、舞鶴港に配備されたイージス艦「みょうこう」「あたご」に長距離巡航ミサイル「トマホーク」の発射機能を付加する改造経費を盛り込みました。
海上自衛隊舞鶴基地では、トマホークを配備するための弾薬庫3棟の増設、総監部司令部の地下化・強靭化が進められ、港湾の浚渫工事が行われています。さらに京田辺市、精華町にまたがる陸上自衛隊祝園分屯地では、東洋最大規模の弾薬庫を更に増強するために、14棟増設が計画されており、既に第一期分8棟の造成工事が8月から強行されました。
2014年には近畿地方で唯一の米軍施設である経ヶ岬通信所が自衛隊基地に隣接してつくられ、ミサイル防衛の早期警戒レーダーが配備されました。配置部隊である米陸軍・第14ミサイル防衛中隊は、米国ハワイ州に拠点を置く第94陸軍航空ミサイル防衛司令部の所属で、米国のミサイル防衛と一体、敵基地攻撃を一体に行う統合防空ミサイル防衛を担う部隊の一つです。
京丹後市や舞鶴が米軍と一体に出撃拠点となり、そのバックヤードとして祝園弾薬庫に大量のミサイルが備蓄をされ、有事の際には鉄道輸送、京奈和道や京都縦貫道など幹線道路を使って舞鶴や西日本方面への陸路輸送が想定されていることが、わが党の堀川あきこ衆議院議員の国会質問でも明らかになりました。
7月9、10日福知山駐屯地の陸上自衛隊第7普通科連隊と在日米軍が参加し日米合同訓練が行われましたが、本来であれば中部方面総監部から近畿中部防衛局に事前に連絡があり、地元自治体や府に知らせることになっていますが、今回はその連絡もありませんでした。地元代表が参加する「安全・安心対策連絡会」では、事実確認を求めたところ、中部方面総監部の担当者は「人事異動で担当者間の引き継ぎが不十分で連絡がなかった」と認めました。「米軍基地を憂う宇川有志の会」の増田代表は「先の対戦の教訓から生まれたシビリアンコントロールが大きく揺らいでいるということを示している」と怒りの声を上げておられます。
党府会議員団としては、8月6日、京都府に対しても政府防衛省に抗議をすること、事実関係と計画の検証、再発防止策を厳しく求める緊急申し入れも行いました。この間の経緯の中でも、本府は、シビリアンコントロールが踏みにじられたという認識が全くないと強く感じました。
京都府北部の労働組合団体などが6月「戦争するな!平和ネットワーク」を結成されました。また当府会議員団は8月末、弾薬庫増設が始まった自衛隊祝園分屯地の現地調査を行いましたが、そこでは昨年結成された「京都祝園ミサイル弾薬庫問題を考える住民ネットワーク」の皆さんが抗議行動を行っておられました。
1万4000筆に上る住民説明会を求める署名の声に押されて、精華町、京田辺市では7月に1回だけ住民説明会が開かれましたが、近畿中部防衛局の担当者からは、立地や弾薬庫の形式、工事期間や内容についての説明があったのみで、保管される弾薬の種類や火薬の量など具体的な住民の不安については「自衛隊の能力が明らかになる」と回答を拒否するなど住民の不安に全く答えませんでした。「何を置かれているかも分からないのに白紙委任できない」「国の機密だから言えないでは納得できない。まず工事を止めてもう一度住民が納得できる説明会をやるのが筋」などの声が上がっています。
そこで知事に伺います。この間の動きは憲法の平和原則やシビリアンコントロールを踏みにじり、京都府全域がアメリカの敵基地攻撃作戦の出撃・補給基地にさせられ、報復攻撃の的になる危険が迫っているという認識はありませんか。
府民の命と安全を守る立場から国に対して、こうした大軍拡、弾薬庫整備や基地拡充など戦争する国づくりに、明確にノーと言うべきだと思いますが、いかがでしょうか。お答えください。
【西脇知事:答弁】北陸新幹線京都延伸計画についてでございます。北陸新幹線につきましては、日本海国土軸の一部を形成いたしますとともに、大規模災害時において東海道新幹線の代替機能を果たし京都府域はもとより関西全体の発展につながる国家プロジェクトであると認識しております。
敦賀以西のルートにつきましては、与党PT北陸新幹線敦賀新大阪間整備委員会の西田委員長が、本年7月29日にルートの再検証に関して発言されましたが、現時点では国におきまして、どのような枠組みや範囲で再検証されるのかがわからないことから、今後よく国政の動きを注視していく必要があると考えております。
なお、着工後条件につきましては、国が安定的な財源見通しの確保や、収支採算性など5つの基本的な条件を確認した上で着工することになっていると承知をしております。
また、特急サンダーバードにつきましては、JR西日本の社長が昨年12月の記者会見で能登半島の震災復興支援の観点から和倉温泉駅に向けて臨時便を一定期間発車させることは検討できると発言されたと承知をしており、まずJR西日本におきまして臨時直行便の運行について具体的な検討をしていただく必要があると考えております。
その他在来線の整備や生活交通バスの維持、生活の基盤づくりや防災減災対策につきましては、府民の安心・安全の確保に不可欠な取り組みであることから京都府総合計画にも位置づけて取り組んでいるところであり、引き続き着実に推進してまいりたいと考えております。
次に自衛隊施設の強化や日米共同訓練についてでございます。国におきましては、閣議決定された国家安全保障戦略などに基づき、防衛力の抜本的強化として火薬庫の増設などに取り組まれているものと承知をしております。近畿中部防衛局からは、こうした防衛力の強化は、力による一方的な現状変更を許容しない、との我が国の意思を示し、攻撃に対する抑止力、対処力を高めることで、我が国への武力攻撃そのものの可能性を低下させるものであって、国民の安心安全に繋がるものと伺っております。
また、今年7月の地元への事前の情報提供なく実施されました日米共同訓練につきましては、京都府から近畿中部防衛局に対しまして、地域住民に不安を与え、地域との信頼関係を損なうものであることから、厳重に抗議いたしますとともに、防衛省内における連携、情報共有の強化徹底と米軍に関する重要な情報の、府及び京丹後市や地元への迅速かつ確実な連絡について、強く申し入れたところでございます。
いずれにいたしましても防衛力の強化につきましては、我が国の安全保障にかかわる国の専権事項であり、国におきまして国民に対する丁寧な説明と適切な判断がなされるものと考えております。
【島田議員:指摘要望】時間がありませんので要望にとどめます。北陸新幹線小浜ルート、現行ルートは反対という声は多数を占めて世論は明らかでございます。慢性的大渋滞が起きている162号線沿い、鳴滝松本町あたりに巨大な立坑が作られ、桂川ルート、京都駅南北ルートもいずれも右京区を直撃です。
この右京区の高校生が向日市議会に請願を出されました。北陸新幹線延伸の撤回を求める請願で5兆3000億円もの負担、もっと増える可能性があり、人口減少の将来の減少の中で、将来世代の負担がより大きくなる。新たなインフラ整備より既存のインフラが必要だ。こんな懸命な請願趣旨でございました。
ご答弁ずっといただきましたけれども、京都が京都でなくなる。こうした北陸新幹線京都延伸計画、祝園弾薬庫や舞鶴基地強化など大軍拡、そして原発再稼働と貯蔵施設建設など府民の暮らしを脅かす国策に何にも言えない、知事の姿がはっきりいたしました。
府民の命と暮らしに寄り添う地方自治体本来の役割を果たす姿勢の転換がどうしても必要です。広域自治体として市町村を支援し、1人ひとりの府民の願いに寄り添う姿勢が知事には求められます。厳しく指摘をして質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。