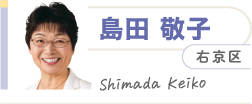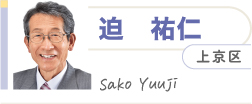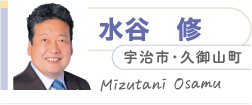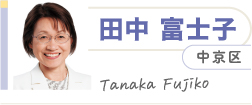9月19日、京都府議会9月定例会一般質問に立った田中ふじこ議員【京都市・中京区】の質疑の大要をご紹介します。
<質疑テーマ>
●障害のある方々のくらしの実態と支援について
●介護保険制度の改善と介護事業所への本府の支援について
障害者の生活を支える事業所への支援へ基本報酬の引き上げを求めよ
【田中議員】日本共産党の田中富士子です。知事並びに理事者の皆さんよろしくお願いいたします。
まず初めに、障害福祉についてです。
2014年に我が国が障害者権利条約に批准し、どんな障害があっても住み慣れた地域で過ごすことができるように制度充実の機運が高まり、障害福祉の充実が求められているところです。2024年度報酬改定が事業所や利用者さんにとってどんな影響が出ているのかを知るために、私は中京区内の事業所にお話を伺いに行きました。ある事業所は医療的ケアの必要な方や重度障害のある方の生活介護や児童のデイサービス、ショートステイなどを行い、医療的ケア児専門員やコーディネーターを配置し相談支援センターの役割も果たしておられます。重度障害者の受け入れ施設は少ない中、障害者の立場に立った支援をされていました。しかし、重度障害者の方は急な欠席や短時間利用があるため、補助金は入るが、「時間刻み報酬」の導入により減収となったと言われます。また看護師を複数配置しないと加算がとれず、昨年と同じことをしていても赤字額が増え、継続の苦しさを訴えられました。
また長年就労継続支援B型事業所とグループホームなどをされている小中規模事業所では、グループホームの入居者さんの加齢により介護度が上り、人員体制を厚くしているが入居者6人に対して世話人1人の報酬となり減収。B型事業所でも時間刻み報酬導入で減収とのことで、光熱費や食費の高騰も堪えるとのことです。2024年度障害福祉報酬改定は、基本報酬を引き下げ、加算での補填となり、更に時間刻み報酬の導入により、生活介護事業所の7割、グループホームの9割が減収となるとともに、小規模事業所の5割で減収となっています。
障害福祉の職員の賃金は、他の産業平均より、月に7万円~9万円低いと言われ、2024年度報酬改定は更に障害福祉の経営難や職員の処遇を悪化させ、障害者支援に大きな影響を与えています。
そこで伺います。2024年度報酬の改定が事業所の経営難と職員不足をさらに深刻にする中、障害福祉の基本報酬引き上げで事業所運営を安定させ、従事者の正規化と非正規労働者を含め大幅な賃金引上げが必要と思いますがいかがですか。
また、新型コロナウイルス感染は規模が縮小しているものの、夏と冬に流行傾向が見られ、今夏の新規感染者数は1年ぶりの高水準となっています。必要時には検査キットを事業所負担で購入し、検査と判定をされています。そこで伺います。事業所への新型コロナウイルス検査キットの配備を無償で行うことが必要だと考えますがいかがですか。
障害者の所得の底上げなど国・府の支援を
【田中議員】次に障害者の所得ですが、2023年度調査では、障害基礎年金1級で月82,812円、2級で66,250円と、生活保護費を下回る水準にあります。障害者のうち生活保護を受給している人は約1割を占め、障害のない人の7倍という多さです。また、5人以上の民間事業所で働く人の平均賃金は、身体障害者は23万5千円、知的障害者13万7千円、精神障害者14万9千円、発達障害者13万円となっています。福祉的就労の賃金・工賃は、就労継続支援A型で86,752円、就労継続支援B型事業所で23,053円となっており、障害者のうち97%が年収200万円以下で、78%が相対的貧困の年収127万円以下となっています。物価高騰や光熱費の高騰が続く中で、障害者のくらしは大変厳しいものです。
そこで伺います。40年間据え置かれている低い障害基礎年金の引き上げや生活保護費の大幅に引き上げなくして生活保障の土台は築けないと考えますが、いかがですか。
次に、障害者のくらしの場についてですが、特に障害の重い人たちは24時間365日支援が必要です。第7期障害福祉計画では、令和4年度末時点より施設入所者数を6%が地域生活に移行するとともに、令和8年度末時点で、令和4年度末の施設入所者数を5%以上削減することを基本としています。しかし、障害者入所施設で地域移行を進めるにあたっての調査では、利用者の地域移行に取り組んでいない施設が35.8%となっています。取り組んでいない施設のその理由は、入所者が地域移行した際に見守りや必要なサービス提供を行う関係機関とのネットワークが不十分であるためとしたのが4割以上、入所者にとって施設の支援が一番適切であるためとしたのが3割以上です。また、私は重度の自閉症のお子さんを持つ方にお話をお聞きしましたが、親亡き後を考え施設入所を早くから考えていたけれど、施設探しに大変苦労されたとのこと、また、お知り合いの方はお子さんを九州の施設に入所させられたとのことで、入所施設が不足しているとお聞きします。
そこで伺います。本府として待機者を把握することで、障害者の入所施設やグループホームが十分か判断できると考えますがいかがですか。
次に障害のある方が65歳になった時の支援の在り方ですが、2010年の基本合意では「介護保険優先原則の廃止」の検討が約束されていたのに果たされていません。65歳になったのを機に介護保険の利用を強いられ、障害福祉サービスの支給を打ち切られたのは違法だとする裁判で、2審判決で勝訴が出ています。介護保険に移行した際に、1割負担が課せられ、介護保険には無い障害者サービスが受けられないことも問題です。
そこで伺います。65歳以上になった障害者には、一律に介護保険を優先とするのでなく、障害福祉制度に従い、介護保険利用者においても、本人の所得による利用料の軽減措置をおこなうことが必要と考えますがいかがですか。
次に福祉就労についてですが、2024年度の報酬改定では、就労継続支援A型事業所の利用者給与が達成されないと施設運営が健全でないと評価され、スコアがマイナス10点、20点、経営改善計画がマイナス50点の判定となり経営悪化を招きました。共同通信社の調査によると、2024年3月から7月の間に、全国329ヵ所のA型事業所が閉鎖となり、働いていた障害者の方が少なくとも5,000人以上は解雇・退職を余儀なくされています。この329カ所のうち4割以上の事業所はB型事業所に移行しているとのことです。府内でも2024年度中に12カ所のA型事業所が廃止となり、あるA型事業所で働いていた方13名のうち12名は変更したB型事業所に就労、1名の方は他のA型事業所に移られたとお聞きしています。私は最近、ある発達障害がある方の相談を受けていますが、A型事業所で働いていたが辞めさせられ、次のA型事業所への就労ができず困っておられます。B型事業所からお誘いがありますが、工賃が300円とのことで断られたそうです。
そこで伺います。2024年度の報酬改定では、A型事業所の報酬にマイナススコア判定が持ち込まれ、生産活動の低い障害者を排除するような事態がおこっていることから、マイナススコア判定を撤回させる必要があると考えますがいかがですか。また、B型事業所は工賃に応じた報酬のために報酬が低く抑えられています。B型事業所の工賃引き上げを支援するべきと考えますがいかがですか。ここまでのご答弁をお願いします。
【西脇知事:答弁】 田中ふじこ議員のご質問にお答えいたします。障害のある方々の暮らしの実態と支援についてでございます。
障害のある方が地域で安心して暮らしていただくためには、各地域において障害福祉サービスが安定的に提供されることが必要だと考えております。障害福祉サービスの令和6年度の報酬改定におきましては、障害福祉分野における賃上げをはじめとする人材確保への対応が喫緊かつ重要な課題であるとの認識のもと、非正規を含む職員の処遇改善のための措置の拡充などによりまして、報酬水準が全体で1.12%引き上げられたところでございます。障害福祉サービス事業所の経営は国が定める公定価格により行われていることから、国の責任において適切な報酬が設定されるべきと考えており、国に対しまして、今回の報酬改定の影響を検証、評価し、安定的に経営を行える報酬水準を確保するよう要望しているところでございます。
京都府といたしましても、事業所の経営改善と職員の雇用の安定や給与水準の引き上げのため、京都府介護・福祉職場業務改善支援センターを核とした事業所の業務改善支援、きょうと福祉人材育成認証制度による人材育成や働きやすい職場づくりの推進、医療機関・福祉施設職員処遇改善等推進事業による福祉人材の処遇改善などに取り組んでいるところでございます。
今後とも、障害福祉サービスの提供体制が確保され、障害のある方が希望に応じて地域で安心して暮らしていただけるよう取組みを進めてまいりたいと考えております。
その他の御質問につきましては、関係理事者から答弁させていただきます。
【井原健康福祉部長:答弁】 新型コロナウイルス検査キットについてでございます。
検査キットにつきましては、5類感染症への移行後は他の感染症と同様、行政からの一律配布ではなく、各施設におきまして検査や医療機関の受診などの必要性を判断し、適切に配備いただいているものと考えております。
京都府といたしましては、重症化リスクの高い方が生活する施設での感染防止対策は重要であることから、5類感染症への移行後も、施設職員を対象としたオンライン相談会を継続して実施してまいりました。また、施設におきまして感染症が発生した場合に適切に対応できるよう、医療機関との連携体制構築のための働きかけや、連携が可能な医療機関の情報提供なども行ってきたところです。京都府といたしましては、引き続き障害者施設が感染防止対策を適切に実施できるよう、支援してまいりたいと考えております。
次に、障害基礎年金及び生活保護費についてでございます。
障害基礎年金を含む障害年金制度は、病気や事故により仕事などが行えなくなった場合の生活を支えるものとして、また、生活保護費制度は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するものとして、それぞれ重要なものと認識しております。これらの給付水準、基準額は、国民生活全体にかかわるものとして国において定められているものであり、障害基礎年金につきましては所得補償の観点から老齢年金と同水準となることを基本に、また、生活保護費につきましては一般国民生活における消費水準との比較により、それぞれ決定されているものと承知しております。年金制度や生活保護制度は国民生活の基本的なセーフティーネットであることから、社会保障制度全体で障害のある方の安定した生活が支援されるよう、国に対して引き続き要望してまいります。
次に、障害者の入所施設及びグループホームについてでございます。
障害のある方がご本人の希望に沿って生活を送られるためには、市町村におきまして障害のある方のニーズを把握し、必要な障害福祉サービスを提供することが重要と考えております。それぞれの地域におけるニーズにつきましては、国が定める基本指針に基づき、市町村が障害のある方の状況やサービス利用に関する意向などを基に把握することとされており、入所待ちをされている方や将来的に入所を希望されている方などのいわゆる待機者の状況につきましては、地域の実情に応じて把握するニーズに勘案されているものと承知しております。
京都府におきましては、市町村が地域のニーズを踏まえて設定した必要なサービス見込み量を広域的な見地から取りまとめ、市町村と連携してサービス提供体制を整備しているところであり、今後とも、地域のニーズに応じたサービス提供体制の確保に取り組んでまいります。
次に、障害のある方が65歳以上となられた際の福祉サービスの利用についてでございます。
障害者総合支援法におきましては、障害のある方が65歳以上になられた場合、原則として介護保険からの給付を優先することとされておりますが、介護保険サービスのみでは適切な支援が受けられない場合などには障害福祉サービスを利用できることとされており、京都府におきましては、市町村に対しましてこうした取扱いの周知を図ってきているところです。
また、介護保険制度におきましては、収入の状況に応じて利用者負担の軽減が図られているところでございます。引き続き、障害のある方が必要なサービスを受けられるよう、適切な制度運用に努めてまいります。
次に、就労継続支援事業についてでございます。
令和6年度の障害福祉サービス報酬改定におきましては、就労継続支援A型について、障害のある方への安定的な就労機会の提供とその質の確保、向上を図るために見直しが行われたものと承知しております。この報酬改定の影響につきましては、現在、国において次期報酬改定に向けた検証がなされているところであり、検証結果も踏まえて必要な対応がとられるものと考えております。
また、就労継続支援B型の工賃を向上させていくためには、障害のある方の特性や能力に応じた多様な仕事を確保することが重要であることから、京都府におきましては、京都ほっとはあとセンターにおきまして、仕事の受発注の調整や製品開発、販路拡大などの支援を行っております。今後とも、障害のある方が地域で自立した生活を送ることができるよう、就労支援に取り組んでまいります。
【田中議員・再質問】 御答弁いただきました。今回の報酬改定では、1.12%の上昇ということではありますが、やはり加算が取れない小さな事業所、あるいは加算がとれるような人員体制を置けない、そういうところで規模によっての格差が生まれているというふうに考えます。生活介護の児童の通所事業における一時間刻みの報酬設定は制度の後退であります。
事業者の安定的運営のためには、「日払い」を見直して、人件費の固定費を月払いにすることが求められています。それを時間刻みの報酬にするのでは全く採算がとれないというふうに考えます。あわせて、基本報酬の減額と加算による補填ではやはりこの格差が生まれますので、基本報酬をしっかり大幅に引き上げていただくことが必要ではないかと、そういうふうにお聞きしているところでございます。
また、就労継続A型事業所のマイナス報酬の導入は、生産性を上げるというもとで、生産性が上がらないようなことになる方、障害のある方を選別して排除している、そういうところで解雇が起こっているというふうに思います。そして、働かなければ収入が得られない、こういう方々をどうして支援するというふうになるのか、私は本当に心配になります。このマイナス報酬は直ちに撤回していただきますように、再度国にしっかり言っていただきたいと思います。
再度お答えください。
【井原健康福祉部長:再答弁】 田中ふじこ議員の再質問にお答えいたします。令和6年度障害福祉サービスの報酬改定についてでございます。
先ほどもご答弁させていただきましたとおり、就労継続支援A型の報酬算定におきましては、障害のある方への安定的な就労機会の提供、また質の確保、向上のために行われたものというふうに承知をしております。また、生活介護につきましては、基本報酬算定の方法につきまして、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするというような目的で実施されたところでございます。
その他の項目につきましても、報酬改定の際にはさまざまな施策の目的によって報酬の変更が行われておりますけれども、その影響につきましては、現在、国の方で実態調査を行っておりますので、その結果を踏まえまして、適切な報酬と今後なるようにしっかりと議論していただきたいというふうに思っております。
これまでから京都府としては国に対して要望しているところであり、引き続き国の議論の動向をしっかりと注視していきたいというふうに考えております。
【田中議員:指摘・要望】障害者権利条約では、障害のある方が地域の中で他の人と同様に暮らすことや選択の自由を保障することを定めており、行政はこのことを保障する責任があります。しかし日本の障害施策予算は、GDPのわずか1%弱です。これをOECD各国並みの2%に引き上げずには障害者の地域での暮らしを保障することができません。本府として、障害者のくらしを支える社会的資源を整え、国へ福祉予算の引き上げを求めていただくことをお願いいたします。
京都府が介護事業所支援を積極的に実施せよ
【田中議員】次に介護保険の問題について伺います。
東京商工リサーチによると2024年度の介護事業者倒産は172件と過去最多を記録し、特に訪問介護が基本報酬のマイナス改定が影響し、過去最多の81件だったのをはじめ、通所・短期入所が56件、有料老人ホームが18件と、いずれも増加しています。2025年度上半期も訪問介護事業所の倒産は過去最多の45件にのぼっています。私は6月に中京区内の訪問介護事業所を訪問しましたが、多くが小規模事業所であり、ヘルパー募集の広告が出ている事業所が何件もあり、忙しく訪問に出かけられる職員の姿が見受けられました。事業所へのアンケートへの回答では、「処遇改善加算を使っても職員給料を十分引き上げられず慢性的な人手不足だ。」「処遇改善加算だけでは事業所の収入にはならず経営が悪化しており、基本報酬の引き上げが必要だ」と書いてありました。今ホームヘルパーの募集には、時給1200円~1400円が提示されており、ヘルパーさんを雇うには時給をあげなければならず、人件費を上げれば事業所が経営難となり、事業所の苦境が伺えます。
日本共産党は、介護職員の処遇改善、介護報酬の増額、事業所の継続的支援などを行うために、国庫負担を10%増やし、国の支出を1.3兆円増やすことを提案しています。介護保険の公費負担を引き上げることは、いま、介護の再生を求める広範な有識者や団体・個人の一致した要求となっています。
今必要なのは、介護の事業所が消滅の危機にある自治体に対し、国費で財政支援を行う仕組みを緊急に作り、民間任せでは事業が成り立たない事業所・施設の経営を公費で支えることです。そして給付の充実と、利用者負担の軽減です。しかし、政府は、要介護1、2の方の在宅サービスの保険外しや利用料の2割・3割負担の対象拡大、ケアプランの有料化など利用料の引き上げを狙っており、介護保険制度の導入の趣旨に逆行し、「保険あって介護なし」です。介護の基盤崩壊は、現役世代にとっても重大問題であり、働く現役世代が介護のために仕事を辞める「介護離職」が年間10万人にのぼっています。
そこで伺います。2024年度の介護報酬改定は、介護事業所の経営を悪化させ倒産・廃業に追い込んでいます。介護保険制度のさらなる改悪を進めようとする国に対し、反対すべきと考えますがいかがですか。同時に、介護事業所が安定的に経営できるように、介護従事者の賃金を全産業平均並みに引き上げることを求めるべきと考えますがいかがですか。
府内では中山間地の町村で介護事業所が存続の危機にありますが、その原因の一つが、訪問介護やデイサービスでは送迎に時間がかかり、移動時間と燃料費の負担が報酬に対して見合わないためです。山間地域の人口減少と高齢化割合増の中で、ヘルパー不足が特に深刻となっています。ヘルパーの賃金引き上げと、なり手を増やさなければ事業所の存続はかないません。
そこで伺います。中山間地域の介護事業所の経営難と撤退が相次いでいることから、ガソリンに対する補助制度や、ヘルパーの賃上げ支援に踏み出すべきと考えますがいかがですか。また、更にヘルパー免許取得のための自己負担軽減額軽減の支援も必要と考えますが、いかがですか。
【井原健康福祉部長:答弁】介護保険制度についてでございます。
介護を必要とする方の増加にともない、介護給付費や保険料、サービス利用料は年々加傾向にあり、給付と負担のバランスを取りながら安定的な制度としていくことが求められております。このため、京都府といたしましては、制度の見直しにあたっては高齢者の生活実態を踏まえた適切な対応を行うことや、持続可能な制度構築に向けて国の負担割合の増加を含め積極的かつ抜本的な見直しを行うことを、国に対し求めているところでございます。
また、介護従事者の給与水準の引き上げにつきましては、国において報酬改定や補助制度の創設が逐次実施されてきたところですが、介護事業所は国が定める公定価格により経営を行っていることから、国の責任において他業種との賃金格差の解消を図るよう、今後とも強く要望してまいりたいと考えております。
次に介護事業所への支援についてでございます。
介護事業所の経営は、長期化する物価高騰、人件費の上昇などの影響で厳しい状況にあり、特に中山間地域の事業所では利用者の減少や移動距離が長いことなどにより運営が厳しいとの声を聞いているところでございます 。介護事業所は、国が定める公定価格で運営されることから、国の責任において適正な対策が講じられるべきと考えており、京都府といたしましては、関係団体や事業者の声を丁寧にお聞きするとともに、国の社会保障審議会などの議論を引き続き注視してまいりたいと考えております。
京都府では物価高騰への対応や経営支援の観点から、物価高等対策事業や処遇改善加算の取得促進のためのセミナーなどを行い、介護事業所の運営を支えているところでございます。
またヘルパー資格取得のための支援につきましては、国において費用の一部を支給する制度がございますので、制度の周知を図ってまいりたいと考えております。今後とも府民の皆様に必要な介護サービスの提供が継続できるよう介護事業所の支援に取り組んでまいります。
【田中議員・再質問】山間地域の方では利用者が減っているというふうにおっしゃいましたが、ほんとうにそうなんでしょうか。ヘルパーのなり手不足、事業所の経営難という中で、ヘルパーさんにも来てもらえないという状況が(施設)入所を早めていると言うこともお聞きします。また、和束町では生活介護の要求が強い中で、特にヘルパーのなり手が無いと言うことなので、十分な介護が(提供)できないという状況があるので、利用が減っているとは一概には言えないのではないかと思います。
本府では、令和7年度訪問介護等サービス提供確保支援事業をされていますが、そもそもヘルパーのなり手がいないのは、仕事内容に比して低賃金だからと考えます。ヘルパーの賃金の引き上げなしにはヘルパー不足の解消はできず、事業所の経営を支えてこそヘルパーさんの賃上げができると考えます。そういう点において山間地域で事業所を支えるための支援に府が乗り出すことが求められています。再度お答えください。
また新たなヘルパーを確保するにはやはりヘルパー免許取得というのが課題でありまして、公的な制度もありますが、また府としても支援ができたらお願いたいと要望いたします。
【井原健康福祉部長:再答弁】中山間地域への事業所への支援についてでございます。令和6年度の介護報酬改定においては、利用者が広域に点在し事業所の運営効率が上がりにくい中山間地域におけるサービス提供を継続する観点から、中山間地域に居住する利用者へサービス提供を行った場合の加算措置などがなされたところでございます。それでもなお事業所の運営環境が厳しいとの声を聞いており、国に対し、中山間地域のサービス提供の実情を踏まえたさらなる加算率の引き上げなどについて要望しているところでございます。
また京都府といたしましても、中山間地域も含めた介護事業所におきまして、長期化する物価高騰への対応や介護従事者の人材確保・定着を進める観点から、物価高騰対策事業やきょうと福祉人材育成認証制度の推進、京都府介護福祉職場業務改善支援センターにおける相談対応により、介護事業所の実情に合わせたきめ細やかな支援を行ってまいりたいと考えております。
【田中議員:指摘・要望】自治体では、訪問介護サービスがなくなれば地域での暮らしが成り立たなくなるという強い危機感から、様々な努力がされています。事業所もそうした使命感を持って日々奮闘されています。そうした努力に京都府が寄り添うことが何より求められます。そのことを改めて求めて質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。