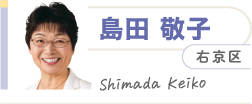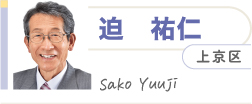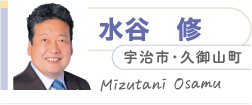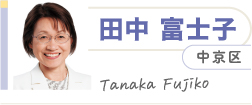10月24日日京都府議会は、決算特別委員会・知事総括質疑をおこない、日本共産党京都府会議員団からは森よしはる議員が質疑に立ちました。
質疑の大要は以下の通りです。
中小企業への直接支援で賃上げを
【森議員】日本共産党の森吉治です。通告により質問させていただきます。
まず、中小企業に対する賃上げへの直接支援についてです。大企業が空前の利益をあげ国の年間予算の5年分にあたる550兆円を超す内部留保を積み増している一方で、中小企業の倒産・廃業が急増しています。
明らかに物価高騰への対応など政治の無策が原因です。東京商工リサーチ社は今年上半期の全国の企業倒産が前年比1.5%増え、5172件となり、12年ぶりの高水準になったことを明らかにしました。人手不足や物価高騰による小規模企業の倒産が目立つとして、「経営体力のない企業が大企業に追いつけず倒産に至っている」さらに、「賃上げに対応できない中小企業の淘汰はこれから本番を迎える可能性が高まっている」と警鐘を鳴らしています。
府内の商工会関係者からも、賃上げについていけずに倒れる企業が出始め、「賃金を上げれば倒産」「賃金をあげなくても倒産」ともうにっちもさっちもいかないという声があがっています。
京都は最低賃金の引き上げを11月21日、秋田県は3月末まで実施を遅らせています。そのこと自身は労働者の生存権に係わる大きな問題ですが、中小企業の事業者から見ればそれほど追いつめられているということではないでしょうか。そうした現場の労働者と中小企業の思いに京都府が心を寄せる時です。
そこで伺います。もはや賃上げのために中小企業を直接支援することなしにこの事態は乗り越えられないのではないかと考えます。その点の認識を伺います。いかがですか。
【西脇知事:答弁】中小企業の賃上げへの直接支援についてでございます。賃金の引き上げは労働者の生活の安定と向上が図られることにより、経済の好循環をもたらす、さらには地域経済の活性化にもつながることから 重要だと考えております。9月に京都商工会議所が支援先など、185社を対象に実施いたしました最低賃金引き上げの影響調査によりますと、最低賃金引き上げが企業の経営に及ぼす影響につきまして「大きな影響がある」と回答した企業は約14%、「ある程度影響がある」と回答した企業は約42%となっております。このような中、賃金の引き上げが持続的に行われるためには、中小企業が原資となる収益を確保できるよう、経営基盤の強化を図るための支援を重点的に行うことが重要だと考えております。また国におきましても、いわゆる骨太方針2025におきまして、賃上げこそが成長戦略の要との考えのもと、中小企業・小規模事業者の賃上げを促進するため、 適切な価格転換や生産性向上、経営基盤の強化を後押しするなど、賃上げ支援の施策を総動員するとされているところでございます。
京都府におきましては、国に対しまして、中小企業が賃上げの原資となる収益を確保できるよう、環境整備を要望いたしますとともに、生産性向上への支援や人手不足対策、金融支援と経営支援が一体となった伴走支援など累次にわたり賃上げができる環境整備のための支援を行ってきたところでございます。また国の方針も踏まえ、今定例会においてご議決いただいた経営基盤強化推進事業費では、賃上げを要件としつつ即効的な経費削減効果がある設備投資等を支援することとしており、持続的な賃上げが可能となるような経営基盤の強化に向けた支援を充実させることで、府内中小企業の事業継続を図ってもらおうと考えております。今後とも中小企業の経営を守るため、あらゆる施策を相談して全力で取り組んでまいりたいと考えております。
【森議員:再質問】再質問させていただきます。56%の企業が賃上げ、最低賃金の引き上げに影響があると先ほど知事もご紹介されました。京都府は昨年度の予算で国の交付金の一部を活用し、中小企業事業継続支援強化事業で賃上げ枠を作られました。 しかし公募はされず、実績は28企業 、京都府が賃上げを確認したのは28人。賃上げはこの点からも広がっていません。生産性向上を図る設備投資等を前提にしていたからではないでしょうか。今年度の当初予算ではその賃上げ枠さえなくなりました。もうこのやり方では、いま問われている「賃上げをしたくてもできない」現状にある中小企業に賃上げを広げることには必ずしも結びついていかないのではないでしょうか。改めて質問します。いかがですか 。
【知事:再答弁】森議員の再質問にお答えいたします。まず令和5年2月補正で出しました賃上げ枠につきましては、ご指摘がありますように28社の採択で、採択した企業 全てが賃上げを実現されました。この賃上げ枠において新たな経営改善につながるような、賃上げを実現するモデル事業が生まれたものと考えており、ここでやられたモデル事業を広く普及させるために、次のステージであります令和6年度の2月補正予算において、賃上げ枠は作りませんでしたけれども、より多くの企業が経営改善が図れるよう生産性向上人手不足対策事業として、予算を大幅に増額し、382社の賃上げを実現したところでございます。いずれにいたしましても、賃上げの持続的に行われるようにするためには、中小企業がその原資となる収益を確保できるよう経営基盤を強化することが重要だと考えております。
【森議員:再々質問】賃上げ支援を実際に行っている自治体は県レベルでも岩手県、山形県、茨城県、群馬県はじめ広がっています。その岩手県では、今年度は2207の法人と358の個人事業主さんから申請があって、26301人の引上げを支援し、予算額は約15億円。今年の最低賃金引上げを受けてさらに追加の支援を検討されています。国の物価高騰対策の重点支援金9億円と県の一般財源10億円で対応しています。
中小企業への賃上げを支援する制度は、知事も即効性を否定はされていません。いま他府県で実施されているように即効性のあることをやらないと生き残れないような切迫した事態にある、こういうのが今の事態ではないでしょうか。また茨城県は今年これまでの生産性向上の設備投資に加えて、1人5万円の直接支援を5年間の目標をもって取り組み出しました。支援の方法を切りかえて紹介したように他府県のような取組みを研究し実施に踏み出すべきと考えますが、あらためて知事の所見をお伺いします。
【知事:再々答弁】直接支援についてでございますけれども、今ご紹介があります自治体につきましては、賃上げを一時的に支援する取り組みだということで理解をしておりますけれども、京都府としては賃上げを継続的に補助金で支援し続けることは困難であり、財政の使い道としてもやはり企業が持続的に賃上げできる体力をつけることによって、幅広く賃上げを実現することが適切な措置だと考えておりまして、引き続きその考え方に基づいて進めてまいりたいと考えております。
【森議員:指摘要望】先ほどの岩手県、茨城県などは メリハリをつけて、今は賃上げの直接支援の時だと、重点的に一般財源も総動員して対応されています。それぐらいのやっぱり厳しい事態が今中小企業に広がっているのではないでしょうか。今年の京都最低賃金審議会の答申は、最後に事業者を一者たりとも取りこぼさない直接的で実効ある大胆な支援を政府に要望すると締めくくっています。同じことは京都府に対しても求められているのではないでしょうか。知事の決断を改めて求めて次の質問に移りたいと思います。
病床削減問題と医療機関の支援について
【森議員】病院の病床削減問題と医療機関の支援についてです。
自民党と日本維新の会が今月20日に政策合意をいたしました。その中身は、国民医療費4兆円の削減を念頭にしたOTC類似薬の保険外し、また、2年後の地域医療構想に向けて病院のベッドの11万床を削減する自民・公明・維新の会の3党合意を今年度中に制度設計をするというものです。国民の命と健康、暮らしにとっても重大問題です。
病床削減の動きはすでに進められていて、京都府では6月定例会に国の病床数適正化、いわゆる削減を後押しをする給付金の予算が提案をされ、ベッド削減が具体化をしてきています。その中には、例えば、人口10万人当たり医師、看護師などが府内で最も厳しい山城南医療圏では、2病院で23床を削減する。また、開業医の数が人口に比して少なく、看護師さんも高齢化などで確保が難しい丹後医療圏においても、府立医科大学北部医療センター10床を含めて21床削減する計画があります。
府立医大病院も10床の削減の意向を示しており、設置者である京都府の責任姿勢が問われます。
全国医学部長病院長会議は、全国81ある国公私立大学病院の2024年度の経営状況について、約508億円の赤字と公表、「このままでは大学病院本来の機能を維持していくことが困難な状況に陥っている、そうした病院も出てきていて、病院閉鎖によって地域医療が崩壊し、国民の健康や福祉に影響が出る恐れがある」と述べています。
そこで、伺います。6月定例会において知事は「病床の削減は基本的にすでに休止中か休止予定であるため、地域医療への影響は生じるものではない」と答弁をされました。
府内では、医療機関がこの事業を活用し削減する意向を示した病床数の合計は2047で、京都府の病床機能報告での休止病床1005をはるかに上回ります。病床数の削減は地域医療に深刻な影響を生じさせることになると考えますが、知事のお考えをお聞かせください。
【知事:答弁】病床数適正化支援事業についてでございます。
今後の急速な高齢化と人口減少が見込まれる中、地域の皆様が安心して医療を受けられる体制を構築するためには、将来を見据えて、効率的で質の高い医療を持続的に提供する体制の構築が必要であると
考えております。そのため、京都府におきましては、各医療圏で設置している地域医療構想調整会議におきまして、地域の事情を踏まえ、医療機関の連携や役割分担の見直しなどの検討を進めており、病床の削減ありきではなく、将来必要な医療体制を整備する観点で取り組みを進めているところでございます。
病床数適正化支援事業につきましては、経営状況が厳しい医療機関の入院医療の継続を目的に実施しており、府内の医療機関に対して行った調査におきまして、2047床の活用意向が回答されたところでございます。活用意向が示された2047床につきましては、各病院におきまして、地域に必要な医療を確保しつつ、平均在院日数の減少、今後の患者の動向などを踏まえ、急症中の病床や稼働率の観点から休症予定の病床につきまして活用を判断されたものであると認識しております。これらの病床は直ちに削減されるものではなく、実際に削減が行われる場合には、京都府として地域医療の影響を確認することとしております。
今回の病床数適正化支援事業で対象となりました291床につきましては、対象となる医療機関に対し、病床の削減が地域医療や新興感染症への対応に影響を及ぼさないことを確認したところでございます。
また、地域医療構想調整会議におきまして、本事業の対象医療機関及び削減病床数を報告し、地域の医療関係者などから意見、ご意見を伺いながら、地域医療への影響について確認を行っているところでございます。今後とも、府民の皆様が将来にわたって安心して医療を受けることができるよう、地域の医療関係者などのご意見をうかがいながら、必要な医療提供体制の構築に努めてまいりたいと考えております。
【森議員:再質問】再質問させていただきます。地域医療が崩壊しかねないとの全国病院長会議での先ほどの警鐘は重く受け止めるべきだと考えます。
知事は影響ないというふうにご答弁されますが、山城南医療圏では、関係者が連携し、努力をいただいていますが、それでも、例えば南山城村では医療機関が1つ、そして木津川市も、人口は2007年の合併時5万8900人から8万人へと2万人以上増えていますが、医療機関数はほとんど増えていません。奈良県や別の医療圏域を利用されている実態もあると聞いています。他県や他の圏域でも病床を削減する動きがあるわけで、全く先は見通せません。丹後医療圏では他の圏域の利用も困難を極めます。
これだけのことが想定されているのに、それでも知事は地域医療に影響は出ないと言えるのでしょうか。
そこで、伺います。指摘したように、地域医療への影響は必至です。
自民・維新政権は、新型コロナ感染症はなかったかのように、11万床の病床削減を医療現場や地域に強引に押し付けようとしています。知事は、府民の命と健康に責任を持つ立場から、こうした動きに反対すべきと考えますけれども、この点についての知事の所見をお聞かせださい。
【再答弁:知事】先ほど答弁いたしましたけれども、医療をめぐる環境は、高齢化、人口減少、また疾病構造の変化と様々な厳しい状況が予想されております。
そうした中で、いかに将来にわたって地域で必要な医療体制を確保するかということが最も重要な観点でございまして、病床の削減ありきではなく、そうした観点から議論を進めているところでございます。
いずれにしても、個別の事業の適用につきましては我々も影響がないことを確認しておりますけれども、最終的には、地域医療構想調整会議の場で、それぞれの医療機関の連携とか役割の分担の見直しなども含めまして、必要な医療提供体制の確保に努め、府民の皆様の命と健康を守って参りたいと考えております。
【森議員・指摘要望】知事は、病床の削減ありきでないという風に言われましたけれども、しかし、今年度中にも11万床の病床削減ということを念頭に制度設計を国の方ではしようとしている動きがあるわけで、今そうした国の動きに対して地方の現場からきちんと声を上げるべきだということを先ほど申しました。
次期地域医療構想にもつながる問題です。先ほど指摘させていただいたように、地域医療の深刻な現実や医療関係者の意見、これを顧みない国のやり方に反対し、地方の現場から国に対して強くこうしたやり方を見直すように働きかけを知事として行うべきです。
危機にある地域の医療機関へ緊急に補正予算を組んで府としても支援を
【森議員】次に、病院が病床削減に応じざるを得ない背景には、公定価格である診療報酬が今の資材費高騰と人件費増などに対応できておらず、医療機関の経営の危機とも言える状況をつくりだしています。先日決算委員会の現地調査で京都大学脳卒中療養支援センターにうかがいましたが、開口一番大学病院はかつてなく厳しい経営実態にあることに言及され同センターの運営も含め支援を要請されました。
全国保険医団体連合会の調査では、物価高を診療報酬で補填できていない医療機関の割合は91.8%、光熱費、医療機器などの材料費、入院患者の食材費など給食費、設備維持管理費などあらゆる面で医療機関の経営を圧迫しています。
全国知事会は8月20日に発表した国への提案・要望の中で「医療機関の経営難に対して診療報酬の臨時改定や国による補助金制度の創設などの対策を早急に講じるよう」求めています。そこで伺います。府として医療機関と府民の命と健康を守るため、国に働きかけるのはもちろん、経営危機に直面する医療機関の支援と看護師さん等の処遇改善を府が独自に今年度補正予算を組んででも行うべきと考えますがいかがでしょうか。知事のご所見を伺います。
【知事:答弁】 医療機関の支援や看護師等の処遇改善についてでございます。
各医療機関におきましては、令和6年度の報酬改定や長期化する物価高騰、人件費の上昇などの影響により厳しい経営状況にある中で、地域で必要なサービスを提供していただくとともに、看護師等の処遇改善にも取り組んでいただいているものと認識しております。
医療機関は、国が定める公定価格である診療報酬により経営を行っていることから、財政支援につきましては国の責任において行われるべきものと考えております。京都府といたしましては、医療機関の経営安定化や看護師等の処遇改善のため、国に対し、全国知事会とも連携して、早急に臨時的な診療報酬の改定や国による補助制度の創設・拡充などの対策を講じるとともに、物価や賃金の上昇が適時適切に反映される仕組みの導入などにつきまして要望しているところでございます。
また、京都府といたしましても、物価高騰が続く中、医療機関などの光熱費等の負担を軽減するための支援や、人材の確保・定着を図るための処遇改善や職場環境の改善に係る取り組みを行う医療機関への支援を実施しているところでございます。
今後とも、国に対しまして、医療機関に対する財政支援などについて強く要望してまいりたいと考えております。
【森議員:再質問】改めてお伺いをいたします。医療現場は、ボーナスを減らしたり、また施設を切り売りしたり、給食の食材調達にも大変なご苦労をされています。今年度の国の事業メニューを受けて、先ほど知事がご紹介された事業を実施をされています。しかし、事態はさらに深刻になっています。緊急に実態も要望も把握をして、京都府として今年度、追加支援などを実施できないのかいうことを改めて求めたいと思いますが、その点、いかがでしょうか。
【知事:再答弁】今言及がありましたように、病院の厳しい経営状況、また現場の処遇改善が必要の必要性につきましては私も十分認識しておりますが、基本的には、公定価格であります診療報酬によって経営の基盤が成り立っている以上、まずは国において適切な対応していただくようにということで、先ほども紹介いたしましたように、早急な臨時的な診療報酬の改定、また国による補助制度の創設、そうした対策によりまして物価の上昇が適宜適切に反映される仕組みの導入を国に求めたいと思っております。
京都府の取り組みにつきましては、いずれにしても厳しい財政状況の中でございますので、そうしたものを踏まえて検討する必要があると考えております。
【森議員:指摘・要望】この点では指摘・要望させていただきます。先ほど言いましたように、医療機関係者が大変な経営危機に陥っています。この危機は政治がつくり出したものと言って過言ではありません。コロナの際には医療現場にあれほど知事も敬意を表されていたと思います。今こそ経営支援と処遇改善、京都府独自に行うべきだ、そのことを強く求めて、次の質問に移らせていただきます。
過大な府民負担強いる京都アリーナは見直しを
【森議員】京都アリーナに関わっての問題です。先ほど知事が厳しい財政状況というふうに言われました。決算審査では、京都府の借金返済に充てる公債費の割合が18%を超えれば、新たに京都府が借金する場合の起債にも国の許可が必要となる実質公債比率が決算で17.1になりました。読売新聞も黄信号の恐れ報じました。府の財政の今後の動向が決算委員会の中でも問われました。知事も記者会見などで不要不急の事業の見直しと言われています。その中で、政府と財界が旗を振るアリーナ・スタジアム改革が全国で2028年のBリーグ・プレミア、この開幕を開幕に照準を合わせて、京都でもアリーナ建設が拙速に進められています。
一方、府立大学の校舎は、耐震性の問題から震度6で倒壊の恐れもあると言われ、待ったなしでの対応が迫られていますが、それなのに、それよりも優先させて京都アリーナに348億円を出す判断をされました。決算委員会書面審査の中でも、塚本府立大学学長は、「校舎整備を急いでいただきたい」こういうふうに発言をされていました。しかし、なぜ京都アリーナを優先させる選択をされたのでしょうか。また、契約では、京都府がアリーナの建設後に事業者から建物を買い取り、維持・運営に関わっては事業者にその対価を払う、こうなっています。京都府の負担が今後348億円から、さらに大きく膨らむ可能性がありますが、そのことをどう考え、どう対応されるのか、知事の所見をお聞かせください。
【知事答弁】京都アリーナ(仮称)の整備についてでございます。
アリーナにつきましては、屋内スポーツ施設の早期整備を求める競技団体からの要望や10万筆を超える署名をいただく中、京都府におけるスポーツ施設の在り方懇話会などにおきまして、幅広くご意見をいただいた上で、屋内競技と自転車競技を合わせた府内スポーツ振興の拠点といたしまして、向日町競輪場において整備することとしたところでございます。
プロリーグや国際大会などの開催により国内外トップレベルのプレーを間近に見られるスポーツ拠点の整備は、子どもたちの夢や憧れの地となるとともに、文化イベントなどの開催は、府民の皆様に出会いや感動、創造を生み出すものであり、将来の京都の発展を見据えたものでございます。
施設整備につきましては、その必要性や緊急性などを総合的に勘案し、判断するものでございますが、アリーナ整備につきましては、将来の財政負担などにも留意しつつ、今必要な投資として、京都の未来づくりのためにしっかりと進めてまいりたいと考えております。
整備につきましては、本件工事はいわゆるインフレスライド条項が適用される事業でございますが、今後、物価上昇に伴う整備費の増額があった場合には、条項に基づいた対応をする必要があるものと考えております。増額要因を抑える取り組みといたしましては、アリーナの機能や品質は同等のままで、コストを下げるVE(バリュー・エンジニアリング)をはじめ、ネーミング・ライツや事業者の収益を京都府に還元する仕組みの導入など、民間のノウハウや創意工夫を生かしながら、コストの低減に努めてまいりたいと考えております。
建設工事管理や運営、モニタリングなどを通じて適切な執行管理に努めますとともに、本事業は長期にわたることから、事業費については必要に応じて精査するなど、適切に取り組んで参りたいと考えております。
【森議員・再質問】先ほど知事も、インフレスライド条項が適用される、こうした点から、今後、348億円の建設にあたってもこれが膨らむという可能性を、今の答弁の中でも示されました。さらに私、指摘したい点は、先日、大阪の、これも1万人の森ノ宮アリーナの計画、これには事業者の手が上がらずに、入札価格をさらに引き上げて再募集するとの報道がありました。こうなりますと、どんどん自治体の負担が膨れ上がります。
今、長崎では、行政に頼らない整備をコンセプトに、通販大手のジャパネットタカタさんが、用地買収も建設も、そして将来の維持・運営も担って地域経済を活性化させようと、昨年、スタジアム・アリーナを作られました。最近できました神戸、そして東京でもトヨタアリーナが作られましたけれども、その整備は民設民営で進められておりまして、アリーナ整備というのはそういう流れが全国にもあります。
そこで、改めて伺いますが、京都アリーナの場合、設計・建設・設備だけで348億円の契約があります。先ほどの知事の答弁でも、インフレスライド条項によって、今後資材費の高騰で上振れする可能性も出てきました。また、維持・管理・運営費は、10年後には大規模改修も含めて府の負担として、これ増え続けます。全国的な流れが今、自治体の負担をできるだけ回避する動きがある中で、京都アリーナについても必要な契約の見直しを行うべきだと考えますが、知事の所見をお聞かせください。
【知事・再質問】森議員の再質問にお答えをいたします。
今、全国の状況のご報告ありましたけれども、この京都アリーナにつきましても、先程言いました、当初から、バリュー・エンジニアリングをはじめネーミング・ライツ、また事業者の収益を還元する仕組み等を含めまして、できる限り民間のノウハウを活用することによって府民負担の軽減を図る仕組みを作りました。それぞれのアリーナには、それぞれの整備上の特徴がございますけれども、我々としては、できる限り府民負担の軽減を抑える観点から、これからも事業者等とも協議をしてまいりたいと思っておりますし、何よりも、全体としてできる限り負担が少なくなるような整備手法について、その都度の節目で我々としてもしっかりと協議をしてまいりたいと思っております。
【森議員・指摘要望】自治体が府民の税金を将来の負担まで、まるごと被ってやらなければ手が上がらない、こうした大規模なアリーナ建設というのは、やはり私、見直しが必要だというふうに考えています。
京都府の財政、大変知事も厳しいという風に言われましたけれども、この財政というのは、私も府の職員やっておりまして、給与カットや人員の削減をはじめとして、本当に身を削って今の京都府の財政を成り立たせてきました。
それを、京都アリーナ建設ということで348億円で、今後の維持・管理については、さらに京都府民の負担になるということについては、私、これまで京都府の財政、府民の宝だと、財産だという風に考えておりましたから、そういった点では、アリーナの整備についても、全国では民間、民設民営ということで、民間のいわゆる体力で整備をするというところが全国の流れになってきていますから、改めてそういったことの検討もこれまでされたのかという点では、極めて拙速に進められてきただけに、そういうやり方について、1度立ち止まって、そういう検証も私は必要ではないかという風に考えているところです。
歩道の拡幅なしに進めるべきでない
【森議員】次に1万人近くが、アリーナが出来た際に帰る際のアクセス道路である向日町停車場線の歩道は人1人分しかありません。知事もご存じだと思います。計画では、拡幅・整備がなくこのまま進められようとしています。進めるべきではないと考えますが、知事の考えかたをお聞かせください。
【西脇知事:答弁】道路整備を含めたアリーナ来場者についてです。アリーナ来場者への対応につきましては、ソフト・ハードが一体となったアクセスルートの円滑化にむけた取り組みが重要だと考えております。ソフト対策といたしましては、公共交通機関を利用した来場を促すとともに、他施設の取り組み事例も参考にしつつ、イベント開催時の入退場時間やルートの分散により、歩行者の混雑緩和が図れるようアリーナ事業者と協力して対応いくこととしております。また、ハード対策といたしましては、府道中山向日線の大原野口交差点の改良や、計画的に進めております都市計画道路・御陵山崎線の歩道整備などに取り組んでいるところでございます。今後とも向日町停車場線も含めまして、ソフト・ハードの両面から幅広い観点で有効な交通対策につきまして検討を重ねてまいりたいと考えております。
【森議員・指摘要望】ソフト・ハード対策を言われました。向日町停車場線ですけれども、知事は「分散する」というふうにルートを考えると言われました。多くの来場者が大挙してこのルートを分散しようと思うと、どこも住宅地に入り込むことになります。閑静な住宅地域でコンサートなどが終わったら、夜の時間が遅くなるということが十分想定されます。向日町競輪場の周辺の道路状況が、そういう状況になっていることも、しっかりふまえた上で対応が必要だと考えています。
自動車でのルートも向日町競輪に近づけば近づくほど、長岡京インター、沓掛インターから車が入る場合も、近づければ近づくほど道路幅が狭くなっておりまして、複雑で渋滞は必至です。
そうしたことの解決は、現状のままでは困難だと考えています。このように地域に様々な形で矛盾を押し付けて、乗り切ろうとする計画は見直すべきです。そのことを求め質問を終わります。
ご清聴ありがとうございました。