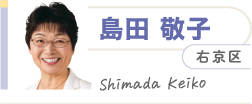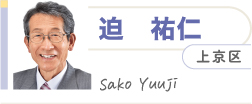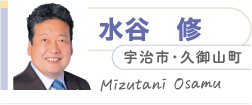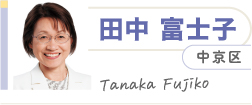6月18日におこなわれた京都府議会6月定例会一般質問に水谷修議員【宇治市・久御山町】が質疑に立ち、「買い物困難者」「買い物難民」の対策や、北陸新幹線延伸計画に関わって、久御山町に計画されている「京都車両基地」や、京田辺市の松井山手駅について知事や理事者に質しました。以下、大要をご紹介します。
買い物困難者・買い物難民に対する行政の抜本的支援を
【水谷議員】日本共産党の水谷修です。一般質問を行います。
まず、買い物困難者、買い物難民についてです。新自由主義による「自治体構造改革」が本格化して30年が経過しました。平成の大合併。合併すれば交付税や財源が増え、地域は豊かになるなどとして、市町村の合併が推し進められました。地方創生という名の政策で地方が疲弊していき、結果は、地方自治体が住民から遠い存在になり、さらに人口減少が進んできたのではないでしょうか。
そうした中、周辺部のまちでは人口減少と高齢化が極端に進行し、商店の激減、鉄道やバスの減便、医療機関や介護事業所も縮小や閉鎖、ATMも廃止。まちが疲弊してきたのではないでしょうか。
京都北部ではスーパー「にしがき」の閉店で困っています。府北部を中心に、最盛期は約30店を経営しておられましたが、2023年に舞鶴市の3店を閉め、今年に入って3月に京丹後市の海部、浜詰の2店を、4月に弥栄と間人の2店を、5月は長岡と加悦の2店の営業を終えました。残るは、京丹後市の2店と宮津市の3店、与謝野町の1店となります。間人では、住民の声、さらに共産党京丹後市議団などの要求に応え、移動販売車が運行されることになったとのことです。
舞鶴市では中心的なスーパーであった地元の「フクヤ」がクスリの「アオキ」に全店代 わりました。昨年「にしがき」が3店舗とも閉店し、2店舗は「アオキ」に変わり、西舞鶴福来店は空き店舗のままです。マナイ商店街はかつて120を超える店舗でしたが、今は25店になり老朽化したアーケードの改修が課題となっているとのことです。東舞鶴の二つの商店街も閉店が相次ぎ、シャッターが目立つ状況です。シニアカー等でしか移動できない高齢者から買物ができず悲鳴が上がっていま す。舞鶴では、さらに、昨年の介護報酬の改悪で訪問介護から撤退する事業所が相次ぎ、訪問介護による買い物を支援するサービスの提供ができなくなるケースも出てきて困っているとのお話をお聞きしました。
南部の地方都市ではどうか。
宇治市などでです。大型店誘導エリアの六地蔵地区でイトーヨーカドー、小倉地区で平和堂、西友が、大久保地区でイオン、久津川地区でイズミヤが相次いで閉店し、買い物困難になっており移動販売車のお世話になっている地域も増えています。
府営住宅の各団地で、買い物困難が増えてきています。西大久保団地は建設時に団地中央に市場を作り小学校も中学校もでき、買い物も便利で賑わいました。しかし市場だった場所はドラッグストアに変わり、入居者や子供が激減しています。そうした中、住民が努力して移動販売を呼び、週2回2箇所に移動販売車が来ています。広い団地で回数や 箇所が少なく、入居者は強く買い物困難を感じておられます。東京都などでは公営住宅で「買物弱者支援事業」として移動販売者の募集や団地敷地での営業を推進しています。
八幡市や京田辺市でスーパーツジトミが閉店するなど厳しい状況で、移動販売車の事業者やスーパー・生協が宅配、移動支援に取り組んでいますが、行政の支援策はありません。
府南部の他の地域でも同様です。
昨年10月の京都新聞は報じました。「京都の玄関口である京都駅周辺(京都市下京区)で、買い物難民が発生しています。昨年夏に老舗スーパーが閉店したことが影響しており、6月からは移動販売車が巡回を始めた。周辺一帯は大規模商業施設が集まる街の中心部だが、住民向けの生活に根ざした店が減っており、高齢者らが不安を抱えている。」とのことです。
農林水産省が令和7年3月に発表した「食品アクセス問題(買物困難者)」に関する全国市町村アンケート調査結果によれば、回答した1033市町村のうち、910市町村、 88.1%が「対策が必要」又は「ある程度必要」と回答しました。また、対策を必要とする背景としては、都市規模にかかわらず「住民の高齢化」が最も多く、次いで「地元小売業の廃業」「中心市街地、既存商店街の衰退」と続いています。また、市町村の多くが財政支援を求めておられます。
農林水産省が行った「地方公共団体が実施している買物困難者等への支援施策」の調査(令和6年3月29日更新)によれば、全国の自治体が行う対策400事例が集約・報告されています。が、しかし府内では1事例しか報告が上がっていません。
お伺いします。
①府内では、地方のまちでも、都市部でも、買い物困難者・買い物難民の問題が深刻化しています。府民の皆さんが困難に直面しているにもかかわらず、京都府総合計画には、買い物難民、買い物困難者について、具体的な記述や対策がありません。農水産物・食品が消費者に届かないなど暮らしの根幹にかかる問題ですが、現状 をどう把握するのか、また、京都府が総合的かつ具体的対策を行うべきですがいかがでしょうか。
②京都府「地域商業ガイドライン」は、大型店の郊外部への無秩序な立地を抑制し、中心市街地での誘導エリアを定め大型店を誘導するガイドラインですが、誘導エリアの大型店が次々撤退するなど、機能していません。商圏の小さい「小商圏の店舗」等を買い物困難地域に誘導などにより、問題を改善すべきですがどうでしょうか。
③全国でも京都でも、地域スーパーと連携した移動販売車が重要な住民の買い物手段になっています。しかし、一定規模の売上が見込めない地域では移動販売車のお世話になれません。多くの自治体が支援を施策化しています。移動販売車の起業や運営、運行を支援する等の対策を行なってはどうでしょうか。また、共食、会食、配食のサービスを制度化してはどうでしょうか。
④地域交通の減便や廃止などが買い物困難者をうむ大きな要因となっていることから、鉄道・バス路線の充実、買い物代行、デマンド交通等を推進してはいかがでしょうか。
【西脇知事:答弁】買い物困難者等の現状把握と総合的かつ具体的な対策についてでございます。
人口減少に伴い、スーパーや商店などが減少し、身近な範囲での買い物が困難な地域が増えております。買い物困難者への対応は、基礎自治体である市町村の役割が重要ではありますが、京都府としても大きな課題であると認識をしております。まず現状把握につきましては、経年の変化は農林水産省が毎年している買い物困難者に関する調査で把握し、実際にスーパーなどの退店が生じた場合には、市町村とともに事業者や地域住民などにヒアリングを実施するなど適切に把握しているところでございます。
また、買い物困難者等の対策につきましては、商店街・商店の活性化や移動販売の仕組みづくり、地域の実情に応じた持続可能で利便性の高い地域公共交通の確保などの対策に取り組んでいるところでございます。
また、地域の商業施設の立地につきましては、まちづくりの観点から市町村がゾーニング等により検討されるものと認識しております。京都府といたしましては、大型商業施設の立地は、近隣の市町村のまちづくりにも影響を与えるため、広域的な観点から市町村の都市計画と整合性を図りながら、郊外部への道無秩序な立地を抑制するため、地域商業ガイドラインにおいて立地可能なエリアを指定しております。
買い物困難者等の対策につきましては、市町村や商業、福祉などの様々な分野の関係者が共同して取り組んでおり、地域のスーパーがなくなった際に、地元自治体や社会福祉協議会等が対策を検討する場に府職員も加わり、買い物の場が確保できた事例も出ているところでございます。
引き続き多様な主体と連携し、地域で買い物ができる環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
【上林商工労働観光部長:答弁】移動販売車に関する支援や共食等のサービスの制度化についてでございます。
移動販売者や共食等のサービスは、住民の毎日の暮らしを支えるものであり、実施主体は様々ですが、公用車による店舗への食料品等の買い出し支援、民間事業者が行う移動販売車による買い物支援、社会福祉協議会による配食サービスなど府内においても多様なサービスが展開されています。
京都府では、中小企業や商店街等が取り組む移動販売サービスにも活用できる補助金を設けており、在庫保管用冷蔵庫やポータブル電源を移動販売車に設置するための経費を支援しております。
またNPO 法人や医師会等が実施する地域の課題解決に向けた取り組みを支援する交付金制度も設けけており、昨年度は地域のコミュニティとなるカフェの運営を支援し、高齢者の引きこもりの防止や会食機会の提供につながった例もございます。今後とも様々な主体と連携し 必要な方にサービスが届くよう支援してまいりたいと考えております。
【石井建設交通部長:答弁】 地域の公共交通の維持・確保についてでございます。
鉄道やバスなどの公共交通は通勤・通学や買い物など地域の生活を支える社会基盤であり、特に車を運転できない方にとりましては欠くことができない移動手段でございます。京都府では、これまでからJR奈良線などの高速化複線化事業の推進、複数市町村にまたがる広域的なバス路線への運行支援などを行い広域的な交通網の整備に取り組むとともにタクシー輸送と買い物代行などの生活支援等一体的に行う事業の実証実験や市町村等が導入するデマンド交通に対する支援を行ってきたところでございます。
また、国におきましては昨年、7月に交通空白解消本部が設置され、今年5月には令和9年度までを集中対策期間として財政支援制度構築等のあらゆるツールの活用強化を図り「交通空白」解消に向けた総合的な後押しを実施していくとの取り組み方針が示されたところでございます。引き続き国の動きを注視しつつ、国や市町村と連携し府民の生活の足となる地域の公共交通の維持確保に取り組んでまいります。
【水谷修議員:再質問】ただいま知事からは、状況は私が述べたような認識はお持ちで、必要性はおっしゃっていました。さらに移動販売の制度、各部署での制度についても、施策が少し始まりかけてるという答弁でございました。しかし現状からすると十分機能がしてなくって事態が深刻化してるというのが実情だと思います。京都府総合計画は、知事が実現したい課題を進めるというバックキャスティング方式で作っています。 府民の困難や困っていること、この問題では買い物できない、食料すら手に入らないという府民の困難に目を向けない方式でその基本的な方針が決められています。
そこで、知事のお伺いしますが、今答弁がありましたように、各部局共通の問題意識を持っているわけですから、買い物難民の問題を地域づくりにとって重要な問題として重要施策に位置づけ、部局横断の対策検討を急ぐべきですが、知事のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
【西脇知事:再答弁】人口減少そして少子高齢化で特に過疎地域における生活サービスの維持が非常に大きな課題になっておりますので、当然買い物困難者対策につきましても重要な政策課題であることは認識をしております。私も就任依頼、連携にこだわること、それから現場を大切にすることと申し上げてきましたので、部局横断というよりも総合的な対策をしていくことが必要だと思っております。ただ、これはもう一方で買い物だけじゃなくて医療とか介護とか単なるその病院への移動とか、いろんな意味で地域においてサービスを維持するという観点からそのサービス間の横の連携も必要だということで考えておりますので、より総合的な対策をするよう努力をしてまいりたいと思っております。
【水谷議員:指摘要望】知事から現状認識と総合的な対策の必要性についてご答弁をいただきました。小さい商圏の店舗展開を進めている地域への商業者も増えています。現状の地域商業ガイドラインも矛盾がございます。移動販売者は今地域のスーパーと連携して運営されており、しかも重要な商業形態ともいえます。起業される方への新たな運行に対する支援は各地で始まっています。是非このことを強化していただきたいと思いまがす。
そして、令和7年3月の農水省まとめた食品アクセス問題についての各省庁の予算の資料によると、いくつかの施策が予算化されています。農家が汗水流して作物を作っても消費者に届かない。巨大港湾や新東名、新名神を建設しても流通が国民に届かない。介護保険の制度後退で介護事業所が減って高齢者に買い物支援できない。京都府は「買い物困難問題をきちんと位置づける」ということを答弁されましたので、早急に対策を強化していただくことを重ねて要望して次の質問に移ります。
北陸新幹線延伸、京都車両基地・松井山手駅について
【水谷議員】北輪新幹線延伸、京都車両基地・松井山手駅についてです。
車両基地の設置場所は、路線の起終点付近が望ましいとされています。しかし北陸新幹線敦賀・新大阪駅が、ほぼトンネルであり、起終点の新大阪駅は地下であるため車両基地を京都に持ってくると言うんでしょうか。
車両基地の主な役目は車両の留置、清掃、整備、検査です。車両留置場として、終点からの移動は営業時間後になるので、深夜早朝の騒音・振動などが懸念されます。この京都車両基地の役目は公表されていませんが、北輪新幹線最大級の白山総合車両所と同規模のようです。
2019年10月台風19号の降雨で千曲川の堤防が決壊し、長野車両基地が水没し、水に浸かり北陸新幹線の全車両の3分の1を廃棄処分にしました。その後、国交省の指導を受け、JR各社は車両基地について浸水想定上の盛土をするよう変えました。そのことを理由に最大9㍍もの盛土、危険な残土捨て場として使われようとしています。
場所は干拓地です。干拓というのは盛土でありません。水をポンプで川に吐き出して陸地にした土地です。ポンプで排水し続けなければ池に戻る土地です。すでに住宅や商業施設開発が進み、治水機能が低下しており、越水・破堤などの場合、浸水する深さが増えます。また、池沼だったのでボーリング調査ではシルト・粘土層が多く見られ、大きな重い構造物を作れば地盤沈下します。そこに巨大な盛土はそもそも間違っています。
自民・公明、そして国や鉄道運輸機構は24年度中にルート決定、25年度着工を強行しようとしていましたが、反対世論と住民運動により断念に追い込まれました。それでも与党などは着工を強行しようとしています。そうした中で、本年3月25日に実施した京都府内の自治体対象説明会では、掘削残土処分などの詳細説明や住民説明会を求める意見もあったと聞いています。
そこで伺います。2回目以降の自治体向け説明会はいつ、どのような内容で実施するのか。また、住民説明会は、日程を含め誰が調整し、どのように実施するのかお答えください。
巨椋池干拓地での30万㎡、最大9㍍の盛土による車両基地建設は、内水氾濫や地盤沈下の危険性があります。車両基地の位置はトンネル区間の場所であるため車両基地からあかり区間までの引き込み線が必要となります。そのため、あかり区間と基地への引き込み線などによる、学校・こども園、住宅地、事業所などのたくさんの立ち退きが生まれます。騒音・振動が予想され、まちと環境と暮らしを破壊する計画であることから、計画の中止を求めるべきですが、お考えをお聞かせください。
巨椋池干拓地が京都府有数の野鳥生息地であり、「久御山町の鳥」であるケリの繁殖地です。またシギ・チドリ類12種の絶滅危惧種の渡り中継地であり、猛禽類の絶滅寸前種のコミミズク、チュウヒや絶滅危惧種6種の生息地です。日本野鳥の会京都支部、日本鳥類保護連盟京都、関西ケリ研究会が、巨椋池干拓地の生物多様性を維持する観点から、「計画の中止」等の「行政勧告」を知事に要望されましたが、どう対応するのかお考えをお聞かせください。
北陸新幹線松井山手駅直近ルート上は、多くのマンション等の高層建築物や住宅の立ち退き、長期の工事による渋滞など、重大な影響が見込まれます。また、駅前広場や関連道路などの建設など大規模な開発となり莫大な財政負担が予想されます。駅建設及び周辺整備の内容や財政規模、自治体の財政負担についてご説明いただきたいと思います。
本年5月12日の建設促進大会で、滋賀県知事は「望んでも求めてもおりません」と明言されました。地元がノーと言えば着工5条件がクリアできないので事業は中止となります。西脇知事は「北陸新幹線の整備は、府民の理解と納得、関係市町の協力が不可欠。地下水を始めとする様々な施工上の課題について引き続き丁寧な説明をお願いします」とのメッセージを送り、京都府も現行ルートでの早期認可・着工を求める「決議」に賛成しています。
まちと環境と暮らしを破壊する北陸新幹線延伸は、受益をはるかに上回る負担となることが明らかであり、京都府の同意がなければ着工5条件が満たせないのであり、知事は「丁寧な説明」を求めるだけでなく「延伸は同意しない」と明言すべきでありますが、いかがでしょうか。
【石井建設交通部長】北陸新幹線にかかる自治体向け説明会及び住民抜け説明会についてでございます。北陸新幹線につきましては、日本海国土軸の一部を形成いたしますとともに、大規模災害時において、東海道新幹線の代替機能を果たし、京都府域はもとより関西全体の発展につながる国家プロジェクトであると認識しております。敦賀―新大阪間につきましては、3月25日に京都府内自治体向けの説明会が開催され、主催者である国及び鉄道運輸機構からは、今回の説明会がスタートラインであると発言があったところであり、引き続き自治体向け説明会が開催されるものと考えております。
また住民向け説明会の開催につきましては、新幹線に限らず公共事業において、直接住民に説明しているケースもあり、そうしたプロセスが必要になることもあると考えておりますが、いずれにしても事業主体である国及び鉄道運輸機構におきまして検討されるものと認識しております。
次に車両基地建設についてでございます。
車両基地につきましては、国及び鉄道運輸機構が昨年8月に提示したルート駅位置の詳細図において、その予定地が示されました。この車両基地予定地は、宇治川と木津川に挟まれた洪水浸水想定区域内に位置しているため、地域の治水への影響が懸念されることから、昨年12月13日の与党PT、北陸新幹線敦賀新大阪間整備委員会におきまして、知事から、施工上の課題の1つとして、車両基地予定地域の治水に対する影響につきましてもお伝えしたところでござい ます。
また、3月25日の自治体向け説明会におきましては、久御山町長から、車両基地の建設計画や周辺地域の治水への影響など、様々な課題について詳細な説明を求める意見が出されたところでございます。
さらに、議員ご指摘の日本野鳥の会京都支部など3団体から、車両基地予定地域における希少鳥類などの保全や生物多様性の維持に関する要望書が京都府に提出されたところでございます。
京都府といたしましては、北陸新幹線の整備にあたりましては、府民の皆様の理解と納得や、関係市町の協力を得ることが不可欠であり、国及び鉄道運輸機構におきまして、治水や自然環境への影響をはじめとする様々な施工上の課題について、十分な時間を確保した上で検討していただく必要があると考えております。
次に、松井山手駅及び周辺整備事業についてでございます。
松井山手駅につきましては、昨年11月の与党PT整備委員会におきまして新駅予定地や駅の構造が示されたところであり、今後、国及び鉄道運輸機構におきまして詳細な検討が行われていくものと承知をしております。
また、建設費の地方負担につきましては、国におきまして財源の確保などと合わせて検討されるものと認識しておりますが、京都府といたしましては、引き続き、国に対し、地方負担が受益に応じた負担となるよう求めてまいりたいと考えております。なお、新駅整備に伴う周辺整備につきましては、一般的には自治体を中心にまちづくりの一環として実施されるものであり、まちづくりを担う関係自治体におきまして、その財政規模も含めて、今後必要に応じ検討されるものと承知しております。
次に、北陸新幹線延伸についてでございます。
北陸新幹線敦賀・新大阪間につきましては、先の自治体向け説明会におきまして、参加自治体から、地下水をはじめとする様々な施工上の課題について影響や問題が生じないとする具体的な根拠を示してほしいなどの意見が出されたところでございます。京都府といたしましては、北陸新幹線の整備にあたりましては、府民の皆様の理解と納得や関係市町の協力を得ることが不可欠であり、まずは国及び鉄道運輸機構におきまして、地下水をはじめとする様々な施工上の課題について、十分な時間を確保した上で検討していただく必要があると考えております。
【水谷議員:再質問】お聞きします。それで、自治体説明会並びに住民への説明会は、いつ、どういうふうに開くんですか。
【石井建設交通部長 :再答弁】水谷議員の再質問にお答えいたします。自治体向け説明会及び住民向け説明会についてでございます。
3月25日の自治体向け説明会におきまして様々なご意見があったところであり、自治体向け説明会につきましては、引き続き開催されるものというふうに考えているところでございます。また、先ほど答弁させていただきましたが、住民向けの説明会につきましても、事業主体におきまして検討されるものというふうに認識しております。
【水谷議員:指摘要望】国交大臣は、京都府に自治体向けの説明会を調整をしていただいているというふうに記者会見で述べておられます。だけど、部長は、いつ頃どういう風に開くんかとお聞きしても全くお答えにならない。私は、6月議会のシーズン終われば早期に開催をしていくように調整を図っていただきたい。そして、住民説明会についても早期に開かれるように調整を図っていただく。ただ、住民が疑問に思っていることをきちんと丁寧に、それこそ丁寧に説明できる準備をして開いていただきたいと思います。車両基地、明かり区間が、計画が示されてから一年近く放置されています。本来はどこに車両基地がどういうものができるのかは、環境アセスの段階、方法書の段階で説明すべきものでした。
それが全く示されないで、突然、巨椋池のど真ん中にくるということが出てきました。発生土の処理について自治体と相談していると国は言っているんですよ。だけど、全くどういう相談をしているのかについてもお答えにならない。自治体に相談しているということは、京都府として発生土の処理について相談しているということですよ。こういうことについても相談を受けているのであればきちんと答えるべきだと思いますし、内容について、それこそ自治体や住民が理解できる内容をきちんと説明するべきです。
松井山手駅についてですが、駅は現在のロータリー付近に二面二線、深さ40メートル、延長330メーター、幅30メーターの大きなもの。しかも国交省は一般的には開削工法だと言っています。あれだけの面積を開削工法で進めると相当大規模な工事になり、立ち退きや長期の渋滞、環境破壊が避けられない。そういうものになってくると思います。この点についても、これから検討されるなどという場合じゃなくて、きちんと国が責任を持って現在の状況、計画、住民にも分かるように説明するべきだということを指摘しておきたいと思います。知事は、府民の理解と納得、関係市町の協力を得ることが不可欠と繰り返しておられます。説明会に、十分疑問に応えられるような内容にしていただきたい。
そして、環境破壊の計画です。また、別ルートを通ったとしても、在来線や地域交通の充実こそ優先すべきものであり、北陸新幹線は延伸すべきものではありません。強くこのことを指摘し、私の質問を終わりたいと思います。ご清聴いただきまして、ありがとうございました。