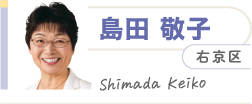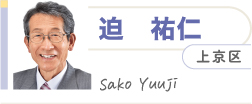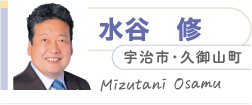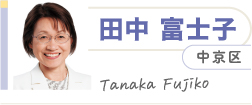6月23日に行われた京都府議会一般質問に立った成宮まり子議員【京都市西京区】の質疑の大要をご紹介します。
事業者丸投げの京都アリーナ(仮称)は住民の声に基づく計画に見直しを
【成宮議員】まず京都アリーナ(仮称)についてです。
アリーナと競輪場再整備の説明会がようやく開催され、私も伺いましたが、多数の疑問や意見が、どの会場でも出たと聞きます。説明会を踏まえ数点伺います。
1つめに、質問が集中した交通対策です。
「物集女街道の渋滞がひどくなるのでは」との疑問に、府理事者は「車での来場は1割以下に抑えたい。車は西側府道へ誘導し、大原野口交差点の駐車場の運用を検討する」と答えました。「アリーナ前の消防署の緊急出動は大丈夫か」との疑問には、「住民の理解と協力で影響が無いようにしたい」とし、「車をどう抑制するのか」と質問には、府は「イベント来場者に呼びかける。電通には実績がある」と繰り返すばかりで、住民が納得のいくものではありませんでした。
「物集女街道に車を通さない」「車を1割以下に抑える」「緊急車両に影響が出ないようにする」など、具体的にどう実行するのか、改めて伺います。
公共交通の利用については、「阪急東向日駅からのメイン道路、向日町停車場線は歩道が極端に狭い。現状のまま、人が殺到すれば危険だ」との意見が何度も出ましたが、府は「経路の分散」ばかりで、道路整備の計画はありません。分散するという西国街道は「住宅地に大勢が入ってきたら困る」と心配されています。
物集女街道の拡幅・改良は、これまでから実施してきてまだ何年もかかり、競輪場直近の箇所は今年から着手です。大原野口の改良もアリーナ開業には間に合わないと聞きます。
向日町停車場線の歩道拡幅をせずに、1万人規模の駅からの来場者や周辺住民の安全が確保できるのですか。物集女街道の拡幅・改良、大原野口交差点の改良の完成は何年先になるのですか。
また、「阪急西向日駅から物集女を通ってくる人もいる。いまでも小学生の通学時に人と車が危険」との声に、府の回答は「これから検討したい」のみでした。西向日駅から物集女のルートは、通学路で子どもたちの安全確保が欠かせません。どう検討されるのですか。
説明会では、「先に道路整備だ。アリーナ建設はそれからだ。順序がちがう」と厳しい声もあり、賛否を超えた多くの住民の思いではないかと聞きました。府として、車や歩行者の誘導、道路・歩道などのハード整備など、住民の疑問や不安に具体的にこたえる計画を示すことこそ先であるべきではありませんか。
2つめに、アリーナ施設そのものや、まちづくりについてです。
「子どもがボール遊び・球技ができる公園を要望してきたのに見当たらない」「バスケコートやコンビニよりも公園がほしい」など声があがりました。昨年6月の説明会でも、また向日市からの要望でも出ており、知事も「子どもたちも球技等で遊べるような形として整備を進めたい」と答弁されたのに、「遊歩道」や「屋根下」しか示されていません。なぜですか。
子どもがボール遊び・球技ができる公園を、今からでも計画に入れるよう求めます、いかがですか。
また、都市計画(地区計画)の変更、「緑地を、遊歩道を含む広場に変更する」ことが、今回の説明会の場で初めて示され、「市民のための緑地を後退させるもの。アリーナを決めてから変更とは順序が逆だ」「説明を一緒にするのはおかしい」などの批判があがっています。
今回の説明会には、地区計画変更の対象地域だけでなく広域から参加者があるもとで、一緒に開催するのは間違っており、別に開催すべきです。いつ対象地区への説明会をされますか。
さらに、向日市議会から本府に対し、市議会への説明を行うように市議会議長名で求めておられます。当然の要望ですが、説明をしないままとなっています。いつまでに説明されますか。
他にも、「住宅地の真ん中に35メートルものアリーナは他に例がない」「いまも工事の騒音がひどい。工事車両が心配」など、さまざまな疑問や意見が出され、説明会のあり方にも「質問は1人1回で、具体的な回答がなかった」「あれで『説明会は終わり』 とされては困る」との声もありました。真摯に受け止め、対応されるよう求めます。
3つめに、隣接する西京区への影響です。
西京区から説明会に参加した方々から交通渋滞など心配する声があがり、5月31日、向日町競輪場周辺道路などの現地調査を行ってきました。物集女街道は、国道9号線千代原口から乙訓へ、常に渋滞し、特に土日など、バスは大幅に遅れ、緊急車両の出動にも影響が出ており、アリーナでさらに大混雑を心配する声があります。府道中山向日線は、9号線から洛西ニュータウンを貫き、「スピードを出す車が多く危険で、迂回車両が殺到したら困る」「南側は道幅が狭く、東山交差点は道路が傾き、大型車両はすれ違いもできない」というのが住民の声です。これらの問題で、住民による「アリーナを考える西京の会・準備会」がつくられ、13日、西脇知事と京都市長に要望書を提出されました。
西京区にも、物集女街道の渋滞悪化、西側府道と大原野口への交通誘導と改修、工事車両など、大きな影響が予想されます。西京区域での府と事業者による説明会を開催し、住民の声を聞き合意が図られるまで工事着工しないでほしい、との要望に応えていただきたいが、いかがですか。
アリーナ問題の最後に、計画全体を民間事業者にゆだねる手法についてです。
本来、住民のためである公共施設が、民間企業任せにより、企業の利益のために歪められ、事業が破たんすれば自治体負担が膨張する事例が全国で問題になっています。さらに政府の「スタジアム・アリーナ改革」では、「スポーツで稼ぐ」ことを成長戦略の柱とし、官民連携・PFIなどにより、スタジアムやアリーナを全国に整備しています。
そのもとで、京都アリーナは、他府県と比べても、348億円を府が投じる契約です。莫大な府民負担があるのだから、当然、府民への説明・合意が必要です。しかし、昨年6月の説明会では具体的内容は「事業者の提案による」と答えず、契約時も金額の積算根拠も「事業者の提案」だとしか答えず、さらに今回の説明会でも、住民の不安や疑問に対し、事業者任せで府が責任を果たす姿勢が見えません。
こんな事業者まかせの方式では、今後一層、住民との矛盾も府民負担も膨らみ、交通対策・まちづくりへの多大な困難を生み、アリーナに期待する人々や事業者にとっても大問題を抱えた施設になってしまうのではありませんか。設計、建設、管理・運営まで任せるやり方は撤回し、あらためて場所の選定や交通・まちづくりとの関係など含め、住民の願いに立脚し、身の丈にあった公共スポーツ施設を計画し直すべきです、いかがですか。
【知事答弁】成宮議員の御質問にお答えいたします。
京都アリーナ整備に係る交通対策についてでございます。
交通対策につきましては、イベントの来場者に車で来場しないよう呼びかけるとともに、大型バス等の関係車両につきまして、道路幅が比較的広い競輪場西側の道路に誘導することで、街道をアクセスルートにしないこととしております。アリーナ事業者の他施設では、車での来場抑止の呼びかけを徹底することにより、95%程度の来場者が公共交通機関を利用しているという実績もあることから、同様の取り組みを徹底したいと考えております。また、最寄り駅から徒歩での来場者に対しましては、時間とルートを分散させることで交通混雑の緩和を図ってまいりたいと考えております。
ハード整備につきましては、代表質問でもお答えしたとおり、周辺道路の交通混雑への対策といたしまして、府道中山向日線の大原野口交差点の改良及び乙訓地域のまちづくりの主軸となります物集女街道である都市計画道路、御陵山崎線の福祉会館前交差点から北側約500㍍区間を本年度から事業着手したところでございます。これらの事業につきましては、地元や関係機関と調整しながら、早期整備に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
また、阪急西向日駅から京都アリーナへのルート上にある通学路の交通安全対策におきましても、現在実施中の事業を含め、ソフト、ハードの両面から取り組んでまいりたいと考えております。
さらに、競輪場の外周道路におきましても、向日市とも連携し、新たに道路を拡幅し、歩道を整備することとしており、通学路における子どもたちを含む周辺住民の皆様の安全確保を図ってまいりたいと考えております。
今後とも、運営実績を有するアリーナ事業者とともに、より効果的な交通対策等の検討を重ねてまいりたいと考えております。
その他の御質問につきましては、関係理事者から答弁させていただきます。
【角田文化施設政策監答弁】アリーナ施設やまちづくりについてでございます。
子どもがボール遊びや球技ができる公園につきましては、安田向日市長からも御要望をいただいており、こうした声にお応えするものとして、バスケットボール広場や遊具広場などを計画しているところでございます。
また、アリーナ整備に伴う都市計画、地区計画の変更に係る説明会につきましては、周辺の住民等の皆様に案内チラシを配布するなどの周知を行うとともに、対象地区内に説明会場を設け、地区計画の変更内容やアリーナ、競輪施設の整備内容について御説明したところでございます。この説明会へ参加いただける方につきましては、手続上、周辺にお住まいの方に限定する必要はなく、広く参加者を募ることについて差し障りはないものとされていることを踏まえ、適切に対応しているところでございます。
また、向日市議会への御説明につきましては、向日市議会において京都アリーナに関する質疑等がされていることは承知をしておりますが、議員御紹介の議長名の文書などはいただいておりません。
いずれにいたしましても、地域の皆様の御意見に対しましては、今後とも丁寧に対応してまいりたいと考えております。
次に、西京区民の皆様からの御要望についてでございますが、先の説明会におきましても、西京区にお住まいの方に御参加いただいたところでございます。引き続き、住民説明会の形式に限らず、ホームページや電子メールによる意見受け付けも活用するなど、あらゆる機会を捉えて、西京区にお住まいの方からも広く御意見を伺いながら進めてまいりたいと考えております。
次に、アリーナ建設の手法などについてでございます。
アリーナ建設につきましては、府内における国内スポーツ施設数が人口当たりの全国比較で劣るという課題認識のもと、京都府におけるスポーツ施設のあり方懇話会において、国際大会等の基準を満たすアリーナ整備の必要性や整備場所などについての御意見をいただいたところでございます。こうした御意見も踏まえ、老朽化が著しく再整備を行う向日町競輪場の余剰地において、屋内競技と自転車競技を合わせた府内スポーツの拠点としてアリーナ整備を行うものでございます。
アリーナの整備・運営に当たりましては、利用者満足度の向上と府民負担の軽減につなげるため、民間のノウハウや創意工夫を生かした手法としているところでございます。単なるアリーナ整備にとどまらず、地域のまちづくりとして、無市や京都市など周辺市町とも連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。
【成宮再質問】答弁をいただきましたが、説明会での説明、そして代表質問への答弁とはほぼ変わる中身でなく、これでは具体的に住民は納得できないと考えます。
2点に絞って再質問させていただきます。まず、交通対策についてです。
「95%徒歩で」という実績があるという話で、そうすると徒歩で来る人が増える。向日町停車場線の拡幅の計画はなしと。これ、沿線の住民や商店は、「歩道の拡幅・改修がないと危険だ」、「店の前で騒がれたら困る、事故や被害が起きる」と言っておられますし、また経路の分散の問題も「西国街道(沿線の方は)困る」と、さっきも言いましたが、声が上がっているわけです。アリーナよりも歩道の拡幅等を含めた交通対策が先だというのが、ある意味、賛否を超えた住民の共通の思いだと思うんですよ。そこに耳を傾けて、府が責任を持って対策を立てていただく必要があると思うんですけれども、なぜそうならないのか、伺います。
もう一点、西京区への影響についてです。知事は比較的西側の府道は広いとおっしゃったんですが、行かれたことあるでしょうか。狭いんですよ、本当に。大型車両が行きかえないということになっております。そして、その中山向日線も大原野口も、そして物集女街道も西京区なんですね。そして、来場者というのは、インターからも来るでしょうから、洛西ニュータウンや大原野上里の生活道路へ入ってくることが予想されます。大きな影響があるのは明らかです。一方で、説明会は、西京区からも来られたという話ですけれども、広報は、向日市では全戸配布し、西京区ではしなかったんです。説明会参加者も、全体631人のうち、西京区からは23人と聞いております。西京区役所支所も、「府からの情報は何もありません」と言っておられます。そこで伺いたいのは、アリーナの西京区への影響というのはどう考えておられるかということなんです。影響はない、説明会を西京区域で開く必要はないというお考えなのかどうか、伺います。
【西脇知事答弁】成宮議員の再質問にお答えをいたします。効果的な交通対策のためには、ソフト、ハードが一体となった競輪場へのアクセスルートの円滑化に向けた検討をさらに深める必要があると思っておりますし、また、将来の新たなまちづくりを支援する道路整備を含めまして、向日市や京都市など周辺の市町とも緊密に連携しながら、ハード整備にも取り組むことが必要だと考えております。
具体的には、御陵山崎線や大原野口交差点などのハード整備とあわせ、アリーナ事業者とともに、より効果的なソフト対策の検討をこれからも重ね、住民の意見も真摯に伺いながら、アリーナ整備を進めてまいりたいと考えております。
その他の再質問につきましては、関係理事者から答弁させていただきます。
【角田文化施設政策監答弁】西京区の説明会でございます。
西京区の影響につきましては、京都市、向日市とも連携しながら、引き続き、より効果的な対策を検討してまいりたいと考えております。先般開催いたしました説明会につきましては、京都府内に在住、在勤されている方を対象として参加募集し、西京区から近い場所にも会場を設け実施したところ、西京区にお住まいの方にも御参加いただいたところでございます。
引き続き、住民説明会の形式に限らず、広く御意見を伺いながら進めてまいりたいと考えております。
【成宮指摘要望】お答えいただきましたけれども、その交通対策、結局、ハード整備や着手しているところは何年先できるかというお答えはありませんでしたし、向日町停車場線については触れもされなかった。これでは納得が住民いかないですよね。向日市民にも西京区民にも具体的な疑問や意見があるのに、府が責任を持って答えていると言えないと考えます。西京区では住民説明会をぜひしていただくように改めて求めておきます。
根本には民間事業者に全て任せる手法にやっぱり問題があると考えます。事業者の丸投げ手法は改め、府が責任を持ち、住民の声を大事にし、住民主役で身の丈に合った計画に見直すべきと指摘し、次の質問に移らせていただきます。
万博体験支援事業による学校行事としての子どもたちの万博参加について
【成宮議員】子どもの万博体験支援事業による学校行事としての万博参加についてです。
万博開幕直前の4月10日、日本共産党議員団は、爆発危険濃度のメタンガスの検出をはじめ、子どもの安全の確保できないなか、万博体験支援事業による学校行事としての参加中止を知事と教育長に申し入れました。さらに、開幕後には万博会場の調査や、教職員・保護者の聞き取りなど進め、さまざまな課題が明らかになっています。
1つは、子どもたちの安全や健康にかかわる問題です。
4月に実施した学校からは、下見ができなかった、下見は代表一人だけで当日の引率が難しかったなどの報告がいくつもあります。府教育委員会の「安全教育の手引き」では、校外学習は「計画作成段階で必ず下見を行い、危険個所と安全対策について確認する」とありますが、万博の場合、そうなってはいないものがあります。
また会場全体に日影が少なく、屋根付きの休憩場所が限られ、「入場ゲートの待ち時間が長く、日差しのなか立ったままで辛かった」「水筒が空になり、給水所は行列で何時間もかかった」という声もあります。具合が悪くなったときの救護施設はたった3カ所しかありません。
高濃度のメタンガスが検知されたマンホールは「立入禁止」の表示のみで、「ガス抜き管が立つそばを子どもたちと一緒に通らねばならなかった」との報告もあります。
昼食場所も、小学生用の団体休憩所は屋根だけで風雨はしのげず、予約制のため炎天下に児童が座り込んで時間待ちする姿もありました。こんななかでも、現場の教職員の必死の努力により、重大なトラブルはこれまでは起きてはいないとしても、「子どもの命を預かる校外学習で、こんなことはあり得ない」というのが教職員などの声です。
万博体験支援事業による子どもたちの参加の実情や実態をどう把握しておられるのか伺います。
現状は、子どもの命や安全を守る対策が不十分であり、今後の梅雨や高温期に向け、熱中症対策や具合が悪くなった時の診療体制、メタンガス対策、休憩所や避難場所などの対策強化が必要と考えます、どう対応されますか。
加えて、ユスリカの大量発生、レジオネラ属菌の基準値以上の発生などが起きています。
レジオネラ属菌は、エアゾルを吸い込むと肺炎など発病の恐れが幼児や高齢者に高いとのことですが、内水面「ウォータープラザ」や「静けさの森」の水盤で、国基準の20倍以上の数値が検出されたと、万博協会は6月5日になって明かしました。1週間前には大阪市保健所からレジオネラ属菌検出速報を受けていたのに、噴水や水上ショーの中止が大幅に遅れ、その間、水盤では子どもたちが水遊びをしていたり、噴水や水上ショーは飛沫のかかる場所で児童生徒が見学していたことも報じられています。
このように安全確認ができていない場所に、子どもたちを校外学習で連れて行くのがいいのでしょうか。レジオネラ属菌対策での安全性の担保をはじめ、猛暑日や豪雨、台風の予想される時などは、学校任せではなく、学校行事としての参加を見合わせることを本府が判断すべきではありませんか。
2つめに、学校教育のあり方と行政との関わりについてです。
「人気パビリオンは予約できず、予約がいらないパビリオンの列に並んだが、1つしか入れなかった」「計画をあきらめて芝生広場で時間を過ごした子どもが多かった」「下見できず旅行業者任せとなり、教師間で十分に議論して子どもの意欲・関心から練り上げた企画でなかった」などの報告があります。
本来、校外学習は子どもたちの発達段階や興味関心、実情と教育目標などをふまえ、現場教職員が議論し練り上げるものであり、子どもたちにとっては、仲間づくりや自然や科学の体験、自らの成長を感じることができるかけがえのない機会だと考えます。さらに「参加は学校の判断」とされますが、実際には子どもを万博に動員することを先にトップダウンで決めたことにより、現場教職員や保護者から不安や反対の意見がつよくあっても、校長など一部の判断で実施されている事例が少なくありません。こうしたやり方は、学校教育と教育行政との関係としてもふさわしくないと考えます、いかがですか。お答えください。
【岡本総合政策環境部長答弁】子どもの万博体験支援事業の実情や実態についてでございます。
大阪関西万博は、子どもたちにとって、国際理解を深めるとともに、未来社会について考える貴重な機会であると認識しており、府内の学校が校外学習など教育の一環として万博会場を訪れる際には、学校からの申請に応じて入場料を支援することとしております。
学校からの報告によりますと、これまで55校、約1万4900人の児童生徒が支援事業を利用して万博会場を訪れております。
また、昨年、学校向けに実施した意向調査を踏まえた想定来場人数約8万6000人のうち、すでに来場した、または日時を決めて仮予約をしているのは約5万2000人と、6割に達しております。これまで来場を予定されていなかったものの、新たに来場を予定している学校も出てきており、着実に事業を利用いただいていると考えております。
次に、万博会場における安全対策と参加見合わせの判断についてでございます。
校外学習等を予定通り実施するかどうかにつきましては、行き先にかかわらず、各学校において、現地の状況や当日の気象情報などを勘案し、判断すべきものと考えております。
万博会場においては、来場者が安全、快適に楽しめるよう、主催者である博覧会協会において、入場ゲートへのスポットエアコンの配備や給水器の設置、テントパラソルによる日差しの抑制などの熱中症対策をはじめ、診療体制の構築やメタンガス対策、休憩所等の確保などに取り組まれているところです。
また、ユスリカの発生やレジオネラ属菌が検出されたことにつきましても、協会において、対策本部の設置や専門家を交えた有効な対策の検討、イベントの休止などの措置が講じられているところです。 これらの対策などにつきましては、協会において報道発表やホームページなどにより広く発信されており、京都府におきましても、説明会や学校向けの専用ホームページなどで学校側に情報提供しているところです。今後も、各学校が参加の可否を判断する材料として、必要に応じ情報を提供してまいりたいと考えております。
【前川教育長答弁】成宮議員のご質問にお答えいたします。万博体験支援事業による学校行事としての子どもたちの万博参加についてでございます。
日本で開催される万博は生涯でも一度あるかないかのイベントであり、今回の大阪・関西万博において最先端技術や命をテーマにした展示を体験することは、未来社会や自身の生き方を考えることができる貴重な機会であると考えております。
もとより、校外学習の内容や行き先につきましては、教育的意義や児童生徒の状況、保護者の負担などを総合的に勘案し、最終的に各学校長が判断されるものとなっております。こうした中、本事業は、京都府において参加を希望する学校を募り、保護者の負担を減らしながら、子どもたちが万博を体験できる機会を持てるよう支援するものであり、学校と行政の関係として適切なものと考えております。府教育委員会といたしましては、本事業の活用なども含め、関係部局とも連携しながら、引き続き、子どもたちの学びの機会がより充実したものとなるよう、必要な情報を提供してまいりたいと考えております。
【成宮議員再質問】ご答弁いただきましたけれども、部長も教育長も、子どもの貴重な機会であるというふうにおっしゃって、保護者の本来の願いは、そうなんですよね。ところが安全対策の面でも学校の校外学習としてもそうなっていないというところに保護者や現場教員の不安があるわけです。 特に、対策として、報道発表やホームページなどにあると、万博協会のいろいろな対策並べられましたけれども、これで学校に判断を委ねるということ自身が大変な負担を学校に強いることだというふうに思うのですよね。
私がお聞きしたいこと、部長に2点あります。
1つは、府としてですね、チケット出すだけじゃなくて、参加した学校から実情や課題をしっかり掴むべきではないかということです。
もう1点は、その上で、今後の対応は参加中止も含めて府が責任を持って判断すべきであり、学校に押し付けて負担を増やすということ、このままでは良くないと考えます。もう一度お答えください。
そして、教育長にもう1点伺います。
何人もの保護者が、学校に万博行きの見直しを手紙に書いたり、校長と面談されたりしているんです。ところが「聞いてもらえなかった」、「休むかどうか家庭で決めてくださいと言われた」という声がいくつもあるんです。保護者の心配や反対があるのに見直さず、家庭や子どもに「行く、行かない」の判断を強いるなどの現状を、これどう受け止められるか、伺います。
【岡本総合政策環境部長答弁】成宮議員の再質問にお答えをいたします。
最初に、学校であるとか、お子様の声をどう聞くかというご質問でございますけども、今、各学校で参加された方の一部の回答ではございますが、実際に手続き等で手間取ったこともある、予約が来ることもあるけれども、実際に、また行くまで課題も多く聞いていたが、実際に行ってみたら生徒の反応はすごく良かった。また、実際に行ってすごく楽しみがここも多かったというような意見も聞いております。
また、最初に申し上げました通り、この大阪・関西万博に実際に府として姿勢を示すということでございますが、これは繰り返しのご答弁になりますが、校外学習等を予定通り実施するかどうかにつきましては、行き先に関わらず、各学校において現地の状況や当日の気象情報などを勘案し判断すべきものと考えております。
【前川教育長答弁】成宮議員の再質問にお答えいたします。各学校での校外学習の決定についてでございます。
校外学習の決定につきましては、各学校がそれぞれの状況に応じて総合的に判断されるものであり、府教育委員会といたしましては、各学校の校外学習の決定、判断に干渉するべきものではないと考えております。一方で、府教育委員会といたしまして、市町教育委員会または府立学校が判断に迷うような場合や相談があった場合には適切に助言してまいりたいと考えております。
【成宮指摘要望】お答えをいただきましたけれども、学校からの報告では、行って良かったの意見が多い、とおっしゃいます。そうかもしれませんが、それにとどめて、課題や問題はないのかということを問うているわけです。そして、教育長、各学校それぞれの判断だとおっしゃいますけれども、そういうことで、このまま進んだら大変な問題があるんじゃないかという問題提起をしているわけです。
そもそも夢洲での万博というのは、カジノを核としたIRの誘致が目的となり、これ自身が問題です。安全対策が後回しになっています。そのもとで入場者数を増やそうと、学校行事として子どもの動員を行政が決めた、現場がそれを押し付けられてるってことが問題だというふうに思うんですね。子どもたちに健康被害などがこれから起きてからでは取り返しがつかないと。これ、本当に共通する保護者や教育現場の教職員の思いなんですよね。大阪府内でも教育委員会として不参加を決めたところもあります。本府も今からでも、今いちど、万博体験事業のあり方を見直して中止すべきということを指摘しまして、質問を終わらせていただきたいと思います。
ご清聴、誠にありがとうございました。