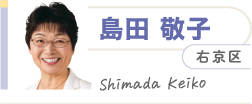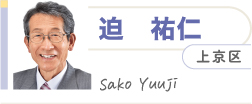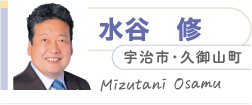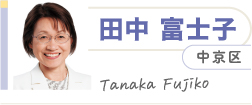9月24日、京都府議会9月定例会一般質問に立ったさこ祐仁議員【京都市・上京区】の質疑の大要をご紹介します。
<質疑テーマ>
●農業における渇水・高温障害に対する支援について
●丹後織物の工賃引上げ、西陣の発展について
農業の渇水対策・高温障害対策の予算拡充を
【さこ議員】日本共産党のさこ祐仁です。通告に基づき知事、理事者に数点お伺いいたします。
島田けい子議員の代表質問の答弁を踏まえ、農業・農村支援についていくつか質問します。
まず、農業の渇水対策・高温障害に対する支援について伺います。
7月の猛暑で、水稲を始め野菜への水が枯渇したため、農家の皆さんは、水を田んぼや畑に供給するために大変苦労をされていました。与謝野町の農業者からは「川から水を取り込むためにポンプを買いに行ったが売り切れていた。水を田に入れられず、田んぼの水は枯渇したままで収穫できなくなってしまう」と悲鳴の声が寄せられました。
党福知山市議団は、7月25日から被害状況を調査し、市独自にポンプの貸し出しと購入のための支援を要望し事業が開始されました。しかし、農業用ため池が干上がり、イネが真っ白で葉っぱも茶色くなり、コメ粒が入っていないこと、万願寺とうがらしも茶色くなってきている状況をお聞きしました。
京都府は8月1日に「水稲渇水対策等支援事業」を開始し、農業用揚水ポンプの購入助成、配水車リースへの補助を決められましたが、ポンプが販売先の在庫に全くない状態で進められています。
9月補正予算では、1億4000万円の緊急的な渇水対策や、高温・渇水に強い農業の振興に向けた支援事業費が提案されました。内容はポンプ整備の支援や給水車に対する支援であり、生産量不足を解決するための待ったなしの対策であることから予算の拡充は歓迎されています。
そこで伺います。農業従事者の生産を継続させるために、来年度も気候変動による高温対策が必要になってくると思いますが、どのように対応されるのか、知事の所見をお聞かせください。
次に、加工用米の契約数量の不足に関して伺います。私は、この5月、加工用米の「京の輝き」で2024年の収穫減による損失補填が発生し、違約金を支払わなければならなくなった、このことの実態について、京丹後市や舞鶴市の農家の方々に実情を聞きに行きました。国制度を活用し出荷契約を締結した加工用米は、JAとの契約した数量の納入が義務化されており、契約数量に至らなかった場合、コシヒカリ等の主食用米で現物納入するか、不足分を1袋30kg、5000円の違約金を支払うことになっているため、農業者は損出補填を余儀なくされています。
丹後大宮町の集落では、地域が凶作で1000袋500万円の身だしが発生し、「補助金はいらないから弁償をこらえてくれ」という農家も出る状況でした。一方、舞鶴市の集落営農法人与保呂ファームは、3年連続で大幅な加工用米の収量不足が続き、2年連続で数百万円単位で損失が出た実態があり、これではもう作っていけないということで、3年目は法人からJAや農政局に働きかけ、にのくに農協が昨年度は高温障害を災害級並だと認め、損失補填はありませんでした。
国は5月19日の参議院・決算委員会で「加工米で契約数量が確保できなかったのは自然災害にくわえ、気候変動による高温障害にほかならず農家の責任ではない」との質問に対し、当時の江藤農水大臣は「自然災害等により減少した場合は、契約数量が確保出来なかった場合、契約数量を変更して交付金を受け取れる」と答弁しています。
そこで伺います。6月定例会の農商工労働常任委員会で、光永議員が畑作物は経営所得安定対策等実施要項に収量低下が認められる合理的な理由として「気候変動」が明記されているが、加工用米には明記されていないことが原因で対応に差が生じているため見直しの必要があることや、少なくとも本年産や来年の作付けに影響が生じないよう遡及対応を求めましたが、本府ではその後、どのように対応されたのかお答ください。また、本年の加工用米が収穫不足に陥った場合、どのように対応されるのか、お答えください。
【答弁:知事】気候変動による高温対策についてでございます。気候変動による高温・渇水の常態化は農作物の収量や品質の低下など、農業経営の安定を脅かすものであることから効果的な対策技術の確立 普及と、生産基盤の強化を進めることが重要だと考えております。
高温対策につきましては、令和5年の高温障害の発生状況を踏まえ、昨年度から高温に強い栽培技術や品種を確立するための実証を行い、有効な資材や機器の導入支援と合わせて迅速に現場に普及を図っているところでございます。具体的には 累次にわたる補正予算を活用し、米の等級を上げるための色彩選別機や乾燥機、施設園芸での乾機や冷房のための空調設備やミスト装置など、府内で約600件の導入を支援したところであり、今後さらに支援を拡充し対策を継続するための予算案を、今定例会に提案しているところでございます。
渇水対策につきましては、本年、府中北部での水稲の被害に対し、緊急的に隣接する別の水路などから農地に水を送るための用水ポンプの導入や、水源が確保できない農地への宮津湾浄化センター放流水などを活用した給水活動に支援したところでございます。
さらに今後の安定的な農業用水の確保に向け、地域内の農業用水の循環利用を図るための農業水利施設へのポンプの設置など、生産基盤の強化に必要な予算案をこの定例会に提案しているところでございます。今後とも農業経営の安定化に向け気候変動に強い生産体制の強化を着実に進めますとともに、販売力の強化やセーフティネットの活用促進など、個々の経営状況に応じたきめ細やかな支援を行ってまいりたいと考えております。
【答弁:小瀬農林水産部長】加工用米の収量不足への対応についてでございます。京都府におきましては、『京の米で京の酒を』のブランド戦略を推進するため、加工用米「京の輝き」を水田農業における重要な品目として位置づけ、生産量の確保に取り組んでいるところでございます。
具体的には、酒米生産者に対しまして主食用米と同程度の所得が確保されるよう国の水田農業の直接支払い交付金による戦略作物助成に加え、産地交付金の重点配分による支援を行っているところでございます。
水田活用の直接支払交付金制度につきましては、自然災害などによる減収で契約数量を満たせない場合、契約数量変更の上で国が合理的な理由があると認める場合には、交付金の交付を受けられるとされており、畑作物と同様、米につきましても気候変動による高温障害は合理的な理由とされ、交付金の対象とされております。
京都府といたしましては、本制度の周知に努めているところであり、減収が判明した時点で、関係者間での契約変更の協議状況を踏まえ、国との事前協議を行うことで交付対象となるよう支援を行ってきているところでございます。本年、中丹、丹後地域で発生いたしました、高温・渇水による酒米の被害状況につきましても、すでに国に報告し、事前協議を始めているところであり、今後、収量減少の要因を明らかにし、計画変更に向けた本格協議を行うなど被害を受けた生産者にしっかり伴走支援をしてまいります。さらに、本制度の交付金算出の前提となります加工用米の基準対象につきまして、選別段階で大粒の米だけをふるい分けするため、出荷量が低下するという酒米の特性をふまえた基準とするよう酒米生産者から強い要望を受けており、国に対しまして改善を求めているところでございます。
今後とも「京の酒」の振興にむけ、国の制度を活用した所得確保や気候変動に適応した京都府独自の技術対策・普及により、酒米の安定供給による生産者や加工流通事業者と一体となって取り組んでまいります。
【さこ祐仁議員:再質問】補正予算も活用して具体的に渇水や高温の対策をされたところもありましたが、ポンプなどの在庫がない状況もあり、購入できなかったところも多くあります。そのよう地域など把握されていると思いますが、来年度も極めて異常な気候変動が続く可能性もあるとのことで、これに対応していくことが求められます。特に中山間地の農家の方々には個人の池がなく、井戸を掘ることで田んぼへの水の確保ができるようにする制度的なものが求められてくると思いますが、中山間地の水田の確保についてどうされるのかお示しください。
また、加工米では、国に対し状況を報告されたということですけれども、加工米で高温障害に合われた方が、確実に保障されるよう求めます。お答えください。
【再答弁:西脇知事】まず高温対策についての中長期的な対応でございますが、当然これからもそうした気候条件が続くことが想定されますことから、これまで導入しました例えば機器への支援ですとか、今回の用水の確保につきましては、中長期的な観点からも取り組んでまいりたいと思っております。
また、中山間地域については、もともと生産条件が非常に不利でございますので、そうしたところでも持続的に農業が継続できるように、農業者の経営状況とか規模に応じた支援が重要だと考えておりまして、今までから共同の機械利用とか集落組織の強化ということに努めてまいりましたけれども、今後とも地域の実態に合わせた省力化、低コスト化による生産性の向上に向けて支援してまいりたいと思っておりますし、その観点にいたしまして高温と渇水対策につきましても、中山間地域に合わせた支援に努めてまいりたいと考えております。
【再答弁:小瀬農林水産部長】契約変更の関係でございますけれども、今年度は中丹、丹後地域を中心に水不足が顕著な水田では、すでに7月の段階から加工用米の大幅な収量減少が懸念された状況でございました。こうしたことから国と事前に協議を行いまして、今年度の高温・渇水による被害状況を報告し共有いたしますとともに、契約数量の変更に向けた具体的な手続き、あるいは変更手続きに必要な資料など事務的な手続きについて協議しているところでございまして、今後、農家さんの要望にあった対応ができるよう精一杯努力してまいりたいというふうに考えてございます。
【さこ議員:指摘要望】加工用米では前年度も被害がでているということなので、対応するよう要望します。コメの増産にむけ、農業者への所得補償、価格保障こそ大事です。米価高騰について、これまで農水省は「コメは足りている。流通の目詰まりが問題だ」と主張してきました。しかし石破政権は、コメ不足が米価高騰の要因と認め、増産を掲げました。農家の方が安心して増産できるには備蓄の拡充と所得補償が欠かせません。「100年安心の農政」を京都府が一緒になって進めることが必要です。要望しておきます。
丹後織物の工賃引きあげ、西陣織物の発展を
【さこ議員】まず、丹後織物の工賃引き上げについて伺います
京都地方最低賃金審議会は8月27日、府内の最低賃金を現行の1058円から64円引き上げて1122円とするよう京都労働局長に答申しました。このことは、京都の織物業界にも大きな影響を与えることになると思っています。もともと丹後地方は、日本の和装用白生地の60%を生産するわが国最大の絹織物産地です。ところが、京都丹後織物業に従事する家内労働者などの最低工賃額を2014年に改定したままで11年間も変更がありませんでした。
この8月に、京丹後市網野町で織物業をされている方を訪問して状況を伺いました。「以前は、街中を歩けばいろんなところから織機の機音がガチャン、ガチャンと途切れることなく聞こえてきていたけど、今はその機音を聞くことの方が珍しい」と話された。私が最初に丹後の織物業者や賃機さんなどを訪問して話を聞いていた18年前当時と全く違っている状況でした。
京丹後市の織機の台数は昨年(2024年)9月に丹後織物協同組合員機業実態調査の集計で稼働台数が1144台とのことでした。2016年に3555台からすると8年間で3分の1に減少しています。
実際にお話をお聞きした男性は年齢75歳で、ご夫婦が織機3台で織られていました。以前は、朝8時から夜8時まで12時間働くのは当たり前だったが、最近は週6日間で1日10時間程度、休憩時間は1~2時間くらいとっているけど、製織遅れや所用で休んだりすると労働時間を延長して頑張っているとのことでした。
月に織機1台7万円くらいの賃金だそうです。京店直接の織屋は高いかもしれませんが、交渉しない人、代行店言いなりの人、仕事量が少ない織屋は低い賃金だそうです。また、取引先を変えて最初の工賃が低いと、頑張ろうとする気が失せてしまうという話が、賃織仲間の会話で出てくるとのことです。
かつて、京都丹後絹織物業に従事する家内労働者などの最低工賃額が2014年10月に13年ぶりに引き上げられました。最も高い京都労働局は全5品目平均で32・7%の引き上げを決定されました。しかし、委託者・受託者・代行者など、複雑な販売・生産体系のある着物業界では最低工賃が守られない状況がありました。その当時、織物業界で最も高い最低工賃は1498円、1万越し当たり、織物織機を1回ガチャンとやる、これが一越ですが、時給に換算すると750円程度にしかならない。63円の値上げになったそれまでは、この金額が払われていなくて、最低工賃が割れる状況で、実際のところ、地元の職人さんのところに入っている工賃は、時給が200円から300円台という状況でした。
厚生労働省は今年の3月、全国的にも家内労働の最低工賃を原則3年ごとに見直していたものを必要に応じて2年に早めるなど機動的に対応することを決めました。最低工賃は、家内労働者の委託者が家内労働者に支払うべき工賃の最低額で物品の一定単位ごとに明示。経済情勢や最低賃金が急激に変化していることを勘案し、工賃のみならず工程、規格なども見直すことを確認したと発表されていますが、その内容が織物関係者にきっちりと伝わることが大事だと思います。
先ほど述べたように2014年に丹後地区の絹織物業の最低工賃の改正が行われましたが、9年以上経過した2023年秋に、京都労働局により、丹後地区内の最低工賃対象の委託者、家内労働者に対し行われた「京都府丹後地区絹織物業家内労働実態調査」の結果や、最近の物価高騰、賃金の引上げなど社会経済情勢を判断して、2024年2月の京都地方労働審議会家内労働部会では、丹後地区の絹織物業最低工賃の改正をしようと、審議が進められております。「この秋くらいに結論が出ればいいですけどね」と京都労働局の方も気にかけておられました。
そこでお聞きします。実際にこの秋に、最低工賃を改正した場合には、委託者はもとより工賃に影響を及ぼしている親事業者、関係団体に対しても、最低工賃が遵守されるよう、本府としてどのように対応されるか、お答ください。
丹後地域でもこれまでは、家内労働者の工賃が上がらない中でも年金収入のある年配の織手が織物の伝統や技術を守って若い織手へ教えながらそれぞれの町の織物を支えてこられました。しかし、現在の物価高騰によって工賃だけでは生活に必要な収入を確保できないことから、子どもに継がせることができないし、子どもも生活できない工賃・金額では継承できないという状況に陥っています。このような状況を改善し、今後子どもも含め若者が継承することのできる賃金形態に引き上げるための支援を国と府が産地とも連携し、支援すべき手立てを一緒に考え、具体化を図るべきと考えますが、いかがですか。
西陣産業の継承・発展について
【さこ議員】京都新聞が、9月3日に西陣織工業組合が3年ごとに行う西陣機業調査の第24次西陣機業調査報告書・調査対象2023年(令和5年)の内容を報道されました。「西陣産地の総出荷額が2023年に169億円と初めて170億円を割り込んだ」と、15年前(08年)の3割規模に縮小した状況との内容でした。
西陣機業のピーク時1975年当時の企業数1129社、織機台数3万2923台、従業者数2万2722人でしたが、2023年の企業数は233社(20.6%)、織機台数2504台(7.6%)、従業者数1692人(7.5%)と減少しています。西陣織工業組合の小平真滋郎理事長は「厳しい結果を真正面から受け止めtr、『オール西陣』で何をすべきか考える一助にしたい」と述べたとの報道でした。
現実に、西陣織そのものを織る後継者・若手が本当に少なくなっています。西陣でも他府県の若者が織物に興味を持ってやって来られますが、賃金が月に15万円代となると生活ができないとして長続きがしないのが実態です。
西陣産業が縮小してきている中、機械設備や道具類、機料品などが不足しており、急いで改善・補充が必要になってきています。また、織手の育成、力織機のインフラの維持、機械のメンテナンス人材の育成の確保などが京丹後、西陣でも求められています。同時に現在も取り組みが始まっていますが、10年後、50年後を見据えて、海外を含む販路拡大を充実させるべきだと考えますが、いかがですか。
【答弁:上林商工労働観光部長】丹後織物の最低工賃の遵守についてでございます。丹後織物産地は、和装需要の大幅な縮小や後継者不足などが進み、大変厳しい状況に置かれております。こうした中、最低工賃の順守は将来にわたり、後継となる職人が育ち、産地を維持していく上で、不可欠であると考えております。最低工賃の改正は家内労働法に基づき、京都地方労働審議会の答申を踏まえて、京都労働局長が決定するものとなっております。改正がなされた場合につきましては、京都府といたしましても、権限を持つ京都労働局や西陣、丹後の産地組合と連携し、委託者、家内労働者だけでなく親事業者、関係団体にも制度内容を周知し、法令遵守の徹底を啓発してまいりたいと考えております。
次に、若者が継承できる賃金形態への引き上げについてでございます。
若者が夢を持って、伝統技術を継承できる賃金にするためには、各事業者が賃上げの原資となる収益を継続的に確保できるよう、和装以外の新たな分野へのチャレンジも重要であると考えております。
そこで、西陣織、京友禅、丹後織物の三産地の組合に加え、京都府も参画するシルクテキスタイルグローバル推進コンソーシアムにおきましては、国内外のインテリアやファッションの分野への進出を目指し、新たな商品開発や市場開拓に取り組んでいるところです。
また、京都府といたしましても新商品開発に不可欠な試色につきまして、京都府織物機械金属振興センターの整形機を活用いただくとともに、インテリア分野への参入を進めるため、昨年同センターに摩耗試験機を導入するなどコンソーシアムでの取り組みを後押ししております。
こうした取り組みの結果、丹後織物と京友禅の事業者の共同による建材が開発され、京都市内のマンションに採用される事例などが生まれているところであり、事例を積み重ね、国内外から受注の拡大につなげることで、新たな収益の柱を作り出し、若者が夢を持って働ける企業が増えるよう取り組むこととしております。
次に機料品など生産基盤の維持や人材育成、将来を見据えた販路開拓についてでございます。
設備の老朽化と修理のための部品不足など生産基盤の維持が課題となっていることから、京都府におきましては、設備の修理や更新、道具類の共同発注などに助成を行うとともに、機料品店の連携組織を設立し、機料品の共同仕入の共同化や機械金属業との共同による代替機料品の開発に取り組んでいるところです。不足する織手や織機のメンテナンス人材の育成につきましては、丹後・西陣産地において正職技術やメンテナンスなどの研修を京都府が実施するとともに、人材の確保に関し人材不足が深刻な丹後地域を対象に、織物業への就業に関心がある学生等を全国から募集して丹後でインターンシップを行う取り組みを今年度から実施しております。
販路拡大につきましては、受注の拡大により、将来の収益を確保するためにも重要であると考えており、東京で三産地合同の展示会を開催するとともに、パリやミラノでの国際見本市に出店し、丹後織物事業者の金属繊維織物が海外有名ブランドの基幹店に採用された事例なども出ております。
府外からの発注は、金属織りなど特殊な技術を要するものが多く、対応できる事業者が限られることから、増加する新たな発注に対応できる事業者を増やしていくことが急務となっております。このため 若手織物事業者の技術取得の勉強会を開催し、産地全体で新たな事業に対応できるよう取り組みを始めているところです。
西陣や丹後の織物業が若者が活躍する産業であり続けられるよう全力で取り組んでまいります。
【さこ議員:指摘要望及び再質問】具体的に販路を広げていくことが、西陣織の具体的に進めてほしいと思っているところであります。また、働く人の賃金を引き上げていくために織物組合等の関係者と協力して進めいくための京都府としても努力するよう求めておきます。
実際、70歳代の織職人の方たちは、後継者がいなくて「自分らの代で終わりだ」と寂しそうに話されています。これは、コロナ禍後の帯地や着物の出荷額が停滞していることにも表れています。現地にこれまでの着物、帯という和装から洋装へという生活様式の変化に対応する動きが始まっているとして、京都府をはじめ新しい西陣の形をつくるとして服地やインテリアへの挑戦をされている織屋も生まれてきています。そこには西陣の強み、シルク・絹糸を使っていること、糸で絵柄を表現し、どういうものが売れるのか、きっちりと情報を集め、自分らの作品・物を作る取組を進められているところもあります。京都府もそういうところへの支援を外国企業とも連携して進めておられます。西陣織は20数工程から成り立っており、それぞれの伝統の技を後世へ伝えていく必要があります。
そこで再質問を1点します。そのものの仕事を通じて伝えていけるように、職人として数人しかいません。京都府が職人育成を支援することが求められますが、いかがですか。
【再答弁:上林商工労働観光部長】関連工程も含めた西陣織産地の人材育成についてでございます。京都府といたしましては、西陣織工業組合の委託や府の織物機械金属振興センターの主催により織手、担い手の人材育成を含め、織機調整や関連工程を含めた人材育成の研修を実施しているところでして今後も業界のニーズを聞きながら必要な人材育成に努め、継承されるよう取り組んでまいりたいと考えていります。